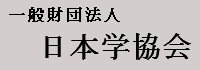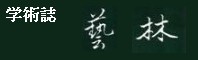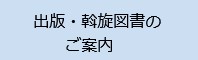『日本』令和7年11月号
文化遺産の保存と継承
仲田昭一 /水戸史学研究会代表理事
自然災害の拡大化
「地球は生きてゐる」。このところの地球規模での異常気象から起こる各地の災害の状況、山火事、線状降水帯の発生と集中豪雨、山崩れ、大規模地震などの頻発を見て、この言葉を実感してゐる。
具体的には、今年一月に米国カリフォルニア州ロサンゼルス近郊で相次いだ二つの大規模な山林火災。これにより約一万五千ヘクタールが焼失し、約三十人が命を落した。山林火災は、三月には韓国南東部で相次いだ。約四万八千ヘクタールが焼き尽くされ、三十人が死亡し、二千棟を超える家屋が被災した。日本では、今年二月に岩手県北部大船渡市で山林火災が発生した。これは約千二百ヘクタールに延焼したと推定されてゐる。
昨年正月には、能登半島地震が発生し、今年の全国に跨(また)がる集中豪雨続出の被害も計り知れない。平成二十三年三月の東日本大震災の復興も未だしである。世界各地に広がる自然災害、予防と併せて地球規模での対策への覚悟が求められてゐる。
災害は、こればかりではない。人災も多い。その最大のものは戦争であり、日常生活の失火である。そして人間のエゴであり、欲望であり、無関心である。
文化遺産の保護
これらの災害に伴つて、これまで人間が営々と築き上げて来た大小さまざまな文化遺産が、破壊され消滅の危険にさらされてゐる。住民の日常生活の復興に全力を傾倒することは必須であるが、これら文化遺産の救出保護、未来への継承にも留意しなければならない。自然災害にはなかなか抗しきれないが、歴史伝統、文化遺産は人間の叡智で護ることが出来る。
卑近な例を紹介する。平成二十三年の東日本大震災で倒壊した個人所有の観音堂(茨城県那珂市)。壊滅状態となり、解体廃棄されるところであつたが、それらの整理を担当した。厨子(ずし)に納められてゐた三十センチメートルほどの聖観音像、その胎内に記された墨書きを見出し、永仁五年(一二九七)に仏師定快(じょうかい)が浅草寺の部材を以て彫つたものと判明した。像は本寺常福寺に迎へられ安置された。
同じく被災崩落した商家の土蔵(茨城県ひたちなか市)。ここからは、天正十七年(一五八九)の起請文(きしょうもん)が出てきた。米沢の伊達政宗が、南方常陸太田に拠る佐竹義宣(よしのぶ)を挟撃しようと、さらに南方の額田昭通(ぬかだあきみち)に送つたものであつた。この文書は、茨城大学の研究室によつて解明された。この研究室は、やがて史資料の救出保存を担つて編成される茨城レスキュー隊の中核となる。
また、瓜連(うりづら)(茨城県那珂市)の鎮守、素鵞(そが)神社。西野則史宮司は、崩れた本殿内を整理してゐて、南朝方の拠点であつた瓜連城主楠木正家公(大楠公の一族の塑像(そぞう)を発見された。城主正家公存在の物的資料である。
いづれも、災害の中から見出された貴重な文化遺産である。
文化庁の動き
令和六年一月に発生した能登半島地震。国指定重要文化財である上時国家(かみときくにけ)の母屋が倒壊したのを始め、漆塗(うるしぬ)り工芸など数多くの文化遺産が被災した。実に大きな損失である。
文化庁では、これら被災した文化財の復旧・復興のため、文化財ドクター派遣事業(建造物の応急措置に対する技術的支援)や文化財レスキュー事業(美術工芸品等の破棄、散逸を防ぐための支援)を行ふと共に、文化財を守る支へ手の輪を広げる「文化財サポーターズ」を立ち上げた。これら積極的施策は、実に喜ばしい。復興予算の中に、文化遺産の救済保護を十分に加へて欲しいと願ふところである。
今日劣化が進む地域を発展的に継承するためには、地域力の維持と向上が必要となる。そのためには、様々な分野に残る「地域の個性」を自覚し、認識を深めることが重要である。この「地域の個性」を理解し、活用し、継承することは、新しい時代を創造することにつながることでもある。
実際、震災で地域住民の離散が進んだ宮城県石巻(いしのまき)市では、民俗芸能の上演会を催した際、地域住民だけではなく、旧住民が集まり、再会を喜ぶ人々で賑はつたといふ。石巻市に限らず、震災後の東北では、民俗芸能が、地域住民を結びつけるものとして積極的な役割を担つたとされてゐる。これらへの補助予算の計上を是非とも叶へたい。
「明治節」と国家の礎
最後に述べる。十一月三日は、昭和二十三年に制定された祝日「文化の日」である。昭和二十年の敗戦前までは、祝日「明治節」であつた。「明治節」は、昭和二年三月三日に制定されたもので、昭和天皇は詔書の中で「朕(ちん)カ皇祖考(こうそこう)明治天皇、盛徳大業、夙(つと)ニ曠古(こうこ)ノ隆運ヲ啓(ひらかせ)タマヘリ」と明治天皇の御盛徳を称へられた。御雇(おやとい)外国人(がいこくじん)の米国人宣教師ジョージ・ウィリアム・ノックスは、明治時代を評して「日本はヨーロッパが、三百年の努力によつてかちえたところを、わづかに三十年で成就した」と言つてその発展を称(たた)へた。このやうな明治天皇に対する国民の敬慕と景仰の至情が第五十二議会に反映し、貴族院、衆議院の満場一致で制定されたのが「明治節」であつた。
この祝日を認識しながら、私ども国民は、日々の生業(なりわい)に邁進しなければならないが、その中で留意しなければならないことは、文化破壊の最大要因は戦争であるといふことである。この戦争を無くし、平和を維持するためには、命がけの覚悟が必要であること、単に悲惨(ひさん)さを訴へ、「平和」を唱へるだけでは、「平和の実現」は出来ないことを悟り、悟らせる必要がある。
その上で、かつてノックスが称へた「明治の飛躍」に学ぶことである。先人は、先駆する欧米の文化・文明に追ひつき追ひ越せの気魄(きはく)を持ち、併せて国家への忠誠心を以て進んだのである。己(おのれ)と国家は一体のものであり、国家を批判や搾取(さくしゅ)の対象とはして来なかつた。
ここから考へるに、日本文化の真髄は、「無私」の精神を以て永く歴史を積み重ねられて来た皇室、これを戴く君民一体の国体であることを認識したいのである。
ここに思ひを致して、今日の幸ひを実感することである。この皇室の護持と安泰とを図ることが、わが国最大の文化遺産を保護することであり、同時にそれを未来へ継承する方策に知恵を絞らなければならない。私ども国民の務めは、これ以外にはないことを、強く認識したいのである。
それ故に、これを破壊消滅させようとするものの存在は、まさに人災である。これらの存在を取り除くことも災害対策であり、国家の礎を固めることでもあるといへよう。