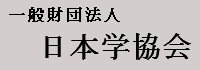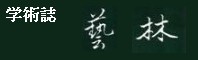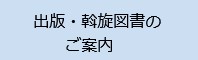『日本』令和7年11月号
大東亜戦争の淵源 ―資料が語るその史実 ―(十一)
アメリカが攻撃されなくとも参戦する
田村一二
一 大統領の詭弁
一九四一年、武器貸与法案の審議中、大統領は護送について「イギリス向けの物資を積んだ船の護送に、アメリカ海軍の軍艦を使うことなど考えていない」(ビーアド『ルーズベルトの責任』三五頁)。「護送は発砲を意味し、発砲は戦争を意味する」(同、一一二頁)と、発言していました。また、法案が成立したなら護送の任務を請け負うことになる海軍省のトップ、海軍長官ノックスも、護送には反対を表明して、「それ自体が戦争行為となる。しかし、大統領の命令があれば従う」と述べたのです(ビーアド前掲書、四九頁、一二七頁)。
厄介な護送の問題を片付けるため議会は、「この法律のいかなる部分も護送を許可するものと解釈すべきではない」との条項を追加して、武器貸与法案はようやく可決されました。
護送は簡単に戦争に発展する可能性があるが故に、民主党内に多くいた戦争支持派は、法案の成立後、間接的に戦争に介入するには、護送が最も効果的であると考えたのです。しかし、武器貸与法は大統領に、護送を指示する権限は与えていません。そこで大統領は、「合法的な『パトロール』は認めるものの、海軍を護送に活用するつもりはない」という趣旨の公式発言を行うのです(ビーアド前掲書、一〇九頁)。
三月末、今度は護送を禁止する決議案が連邦議会に提出されました。そして四月中旬には、「海軍がイギリス商船を護送しているという疑惑」が報道されたのです。大統領は、記者会見で護送や武装防護の疑惑について問われ、「ばかげた話」と一蹴しました(ビーアド前掲書、一三三―一三四頁)。
一方、連邦議会では護送について「大統領の率直で曖昧さのない声明」を求める要望が強まっていきます。
更に護送問題を一層複雑にしたのが、四月十日に発表された「グリーンランドを両国の半球防衛協力の対象とする」というアメリカとデンマークとの合意でした。当然占領地との間には輸送船の往来が必要になってきます。政府は四月二十四日、イギリスへの物資の輸送を確実にするため、アメリカ軍を投入する備えを始めました。同日、海軍長官ノックスは、「わが国の物資が大西洋で沈められるのを許すわけにはゆかない。我々はイギリスを支援するという約束を履行して、この任務を最後まで遂行する」と宣言しました(ビーアド前掲書、一四五頁)。
その二日前、「大統領の指示で」発令、実行されたパトロールに関する計画があります。その計画には次の記載がありました(傍点は原文のママ)。
この計画を実行する際 は、港から出航する時点で通常の海軍の軍事演習の外観を装うこと 」(ビーアド前掲書、四〇九頁、注⒇)。
護送の事実を隠す小細工であることは明らかです。真珠湾調査委員会は次のように厳しく断じています。
資料〔 真珠湾調査委員会「CJCレポート」(真珠湾調査委員の番号がついていない資料)
実際には、アメリカ海軍はこの当時、既に一定の期間、秘密裏にイギリスと協力して「船団」が大西洋を航行し続けられるよう「護衛」任務に従事していた。
(ビーアド前掲書、四〇九頁、注⒃)
㈠ 資料の意義
当時ルーズベルトは、護送を行っていたにも拘らず、「パトロールであって、護送ではない。二つの任務には、牛と馬ほどの違いがある」と発言しています。詭弁以外の何物でもなかったのです。
武器貸与法の運用が、援助と護送と一体となって行われており、大統領の同法に対する国民への説明や約束は、計画的な欺瞞(ぎまん)であったと言わざるを得ません。
㈡ 解説一九四〇年十二月末の炉辺談話で「民主主義の兵器庫」となると、公約を微妙に修正したルーズベルトは、素早く武器貸与法案を成立させ、イギリスへの武器援助を護送付きで行い、戦争一歩手前のぎりぎりまで踏み込んでいくのです。同法は、時の経過とともに、その意味と帰結が明らかになっていき、(ビーアド前掲書、一〇五頁)。孤立・中立政策とは全く異なった外交を展開していくことになるのです。
こうして参戦への堡塁をひとつずつ築いて進むルーズベルトの強い企図が、やがて日本の運命を大きく変えていくこととなります。
二 独ソ開戦 ―― 英国・米国・日本への激震
一九四一年六月二十二日、突如、ドイツ軍がソ連に侵攻し独ソ戦が勃発し、イギリス、アメリカ、日本に激震が走りました。それまで風前の灯だったイギリスの苦境は救われ、ソ連を連合国側に引き入れ、更に日本の国策の根幹を揺るがしたのです。それは、第二次世界大戦の戦局と性格を一変させてしまいました。
㈠ 日本の国策の大転換独ソ開戦は、近衛首相に深刻な衝撃を与え、日本は今まで進めてきた国策の大転換をせざるを得なくなりました。首相は元来、三国同盟に加えてドイツが日ソ関係を斡旋(あっせん)し、ソ連をも加えた四国協商を成立させ、その結果、四国の威圧でアメリカの参戦を阻止(そし)して、同時にアメリカとの諒解をとげて支那事変を解決できる、と期待していました。しかし、独ソ開戦は、この国策を根底から崩壊させました。
首相はドイツの裏切りであり、三国同盟に拘泥(こうでい)するのは危険として、国策の大転換を図り、日米接近、関係改善へと大きく舵を切ったのです。
しかし、時はすでに遅し。独ソ開戦の前日二十一日、アメリカは、日米関係を改善すると称して交渉の基礎案、「六・二一アメリカ案」(加瀬俊一(としかず)著『日本外交史23 ―日米交渉』一四四―一五一頁参照)をこの絶妙なタイミングで日本に送りつけてきたのです。同案の文面は穏やかながら、その実質について練達した外交官である加瀬氏は、その特色を次のように述べています (加瀬前掲書、一六七頁)。
① 援英強化・ドイツ打倒に邁進する方針を暗示し、参戦気構えが濃厚である。
② 三国同盟から日本を離脱させようと苦心している。③ 中国問題に干渉する権利を獲得しようとしている。
④ 日本の経済発展を拘束しようとする底意が覗(み)える。
裏面に隠されたアメリカの意図を読み取った日本は、とても交渉の基礎として受け入れることはできないとの考えもありましたが、政府の連絡会議は「交渉に余地を残すのが妥当」と判断し、何とか活路を見出そうと譲歩を重ねて日米交渉を継続していくのです。しかし、アメリカの態度は、「六・二一アメリカ案」から一歩も引かず、益々厳しくなっていくばかりでした。
㈡ 独ソ戦の行方を見極めるアメリカドイツの矛先は、東方・ソ連へと向けられ、猛攻を受けていたイギリスは窮地を脱します。首相チャーチルは、即日、ヒトラーに激烈なる非難を浴びせた上で「ロシアに可能な限りの援助を与える」ことを宣言します。こうして共産主義国・ソ連を連合国側に引き込んだのです。
一方、アメリカでいち早く反応したのは、陸軍長官スチムソンでした。独ソ開戦は「殆んど神の摂理のごとき出来事」と、この激震を表現しました。しかし、アメリカ軍の専門家は、「ソ連の抵抗は三週間、長くても六週間で終る」とする一致した意見でした。ソ連の脆(もろ)さが指摘されている中、ソ連からの報告が齎(もたら)されたのは、独ソ開戦から二週間後のことでした。結論的には「ソ連陸軍の抵抗が意外と強力であること、ソ連国民の結束は固く、スターリン失脚の可能性は少なく、スターリンは徹底抗戦を貫く」との分析でした。
ルーズベルトは、対ソ援助を考えていましたが、その前にソ連の軍事能力が実際にどの程度のものか、そして自身の世界政策達成にどれだけ当てにできるかを、直接見極めようとしたのです。
七月十三日、最側近のハリー・ホプキンズは、ルーズベルトの密命を受け、イギリスを訪問し、チャーチルと会談を行い、主題は、独ソ戦の見通しと大西洋会談等でした。この時、既に独ソ戦の趨勢(すうせい)が見えてくる四週間に入っており、冬季持久の希望がちらつき始めているものの、確たる見通しは無かったのです。その見通し無くして、八月の大西洋会談の成果は期待できません。そこでホプキンズは、独ソ戦の見通しを得るために、直接スターリンと会談したいと、ロンドンからルーズベルトにモスクワ行きの許可を求めます。ルーズベルトは、「大賛成」と返答し、二十九日にはモスクワ入りして、早くも八月一日にはモスクワを離れます。そのわずかな期間でホプキンズは、スターリンとの会見を行い、ソ連の国力、独ソ戦の見通しなど重要な情報を獲得したのです。ルーズベルトのスピーチライターであるロバート・E・シャーウッド(一八九六―一九五五)は、次のように述べています。
資料
スターリンは、ホプキンズに対して完全な信頼を置いていた。これは英国及び米国とソ連との戦時関係における転機であった。もはや米英の計画はすべてロシアの早期崩壊という蓋然(がいぜん)性の上に築かれることは無いであろう。
⑴資料の意義
「ソ連の早期崩壊はない。持ち堪(こた)える」。この確かな情報は、大西洋会談でチャーチルと戦後の世界政策の擦り合わせを行う重要な前提となり、またソ連への武器支援に大きく道を拓(ひら)くことになるのです。更にドイツと日本に対決していく上での計画の遂行が可能となり、アメリカ参戦への道を拓くものとなるのです。
⑵ 解説①スターリンの期待
「ソ連の崩壊はない」と判断したルーズベルトは、十月一日には、ソ連との間で武器援助交渉を妥結させ、「大砲から長靴まで」の援助を行うのです。独ソ戦で苦戦するスターリンは、難渋した交渉が妥結した時、喜びのあまり四十回もの乾杯を重ねたと言われています。スターリンは、更に一歩踏み込んで、アメリカの参戦を渇望します。「ヒトラーに抵抗するに必要な激励と道義力を得ることが出来るのは唯一つの源泉からだけである。その源泉は米国であり、大統領及び米国政府の世界的影響力は絶大である。もし米国がドイツに宣戦すると発表すれば、兵火を交えずともそれだけでドイツを破り得るかも知れない」(シャーウッド前掲書、三七三頁)。アメリカの参戦こそが、連合国やソ連を勝利に導く原動力であると期待するのです。
アメリカの参戦を今や遅しと、大きな期待を持って待っているスターリンの姿が目に浮かんできます。
②前大統領フーバーの厳しい批判と慧眼独ソ開戦から間もない一九四一年六月二十九日、前大統領フーバーは、ラジオ放送でアメリカ国民に次のように訴えました。(要旨)
ソ連は、歴史上最も血塗られた恐怖政治を進め、人権を蹂躙し、数百万の無辜(むこ)の人々が正義など全く感ぜられない方法で殺された。ソビエトは国際的約束を守らない。民主主義国家に対して破壊工作を進めている。我が国もその標的である。
我が国が参戦し我々が勝利すれば、スターリンはロシアの共産主義を盤石(ばんじゃく)にし、共産主義思想を世界各地に拡大させることになる。
ふたりの独裁者は猛烈な戦いを始めた。どちらの独裁者も間違いなく衰弱する。まともな政治家であれば我が合衆国は、二人の独裁者の戦いを傍観しつつ、防衛力だけはしっかり保持しておこうと考えるだろう。参戦してしまえば我が国も衰弱する。
スターリンと提携することは、我が国建国の精神を踏みにじることになるのだ。ソビエトと協力すれば、我が国は将来必ずそのツケを払うことになるだろう(フーバー『裏切られた自由・上』四二九―四三三頁)。
「アメリカは局外にいて独ソの両独裁者の疲弊を待つべき」、「参戦すればアメリカも疲弊する」というフーバーの警告を、ルーズベルトは聞き入れず、共産主義者と手を握るのです。その行為は、就任早々にソ連を承認したときと重なり、一度ならず二度までも建国の理念を踏みにじったのです。共産主義者と手を握った結果、将来引き起こされるであろう戦後の悲劇を、フーバーの慧眼(けいがん)は見通していたのでした。
三 大西洋会談の実態―参戦への仕上げ
日本の南部仏印進駐を受けて、八月一日、アメリカは対日石油禁輸措置を発動し、日本は国家存立の危機に直面します。近衛首相はこの危機を大局的見地から解決を図りたいと、日米首脳会談を申し入れますが、ルーズベルトはこれには取りあわず、チャーチルとの大西洋会談へと秘密裏に出発します。会談は九日から十二日までニューファンドランド島沖で行われ、帰国直後、明らかにされたのは会談が行われた事実、大西洋憲章と武器貸与法の運用等の議事内容だけでした。緊急とも思われない事項について、ドイツの潜水艦が跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)する大西洋上二千五百マイル(約四千キロ)も、チャーチルが命がけで往復するとはとても考えられません。
実は、大西洋会談で合意されたのは、①対日政策、②アゾレフ島の占領、③戦後の米・英の世界政策構想(後の大西洋憲章)等でした。この隠された真実を真珠湾調査委員会が明らかにしています。
㈠ 対日並行宣言第一の主要議題が対日政策であり、イギリスはアジアにおいて日本の南進の脅威に晒されており、チャーチルは、「合衆国が日本の南進を防ぐ明確な宣言」を出すことを強く求めます(ビーアド前掲書、六一九―六二〇頁)。それが「対日並行宣言」として合意されます。資料はアメリカ政府の草案です。
資料(傍点の原文はイタリック体)
⑴ 日本が西南太平洋でこれ以上侵略を進めた場合 、合衆国政府は、日米戦争になる可能性があっても、対抗措置を取らざるを得なくなる。
⑵ この対抗措置を支持した第三国を仮に日本が攻撃しようとした場合、大統領はその第三国を援助する権限を連邦議会に要請する意思がある。(ビーアド前掲書、六一八頁)
⑴ 資料の意義
ルーズベルトは西南太平洋に限らず、アメリカの措置を支持する第三国を日本が攻撃するなら、「日米開戦」も辞さない決意を示しているのです。「アメリカが攻撃されない限り、参戦しない」という公約に相反する合意です。
⑵ 解説① 日本をあやす
ルーズベルトは、「対日並行宣言」を帰国後に日本政府に発することを約束します。もっと強い措置を望んだチャーチルに、ルーズベルトは、こう言うのです。
また、ホワイトハウスと国務省詰めの記者であるファースト・デービスとアーネスト・K・リンドリーの著書『戦争はいかにして始まったか』の中には、期間のちがいはあるが対日並行宣言を出すことによって、「三カ月はやつら(日本)をあやしておけるだろう」(ビーアド前掲書、七九六頁、注⑺)という日本を侮辱(ぶじょく)した記述があります。
② 合衆国の利益を守るルーズベルトは、帰国後、直ちに野村大使を呼び、やや穏やかな表現に変えて、次のように伝えました。
日本政府が武力または武力の脅威によって近隣諸国を軍事的に支配する政策ないし計画をこれ以上僅かでも推進するなら、合衆国とアメリカ国民の正当な権利と利益を擁護するため、あるいは合衆国の安全と安全保障を確保するため、必要と見なすあらゆる措置を直ちに講じなくてはならなくなる(ビーアド前掲書、六五七頁)。
「その利益を守る」とは、「合衆国が遅かれ早かれ、実際的行動に出る」(ビーアド前掲書、六五八頁)という意味であり、即ち「戦争をも辞さず」。それが大統領の決意です。
㈡ 大西洋憲章 ―― 米・英による戦後の世界支配第三の合意は、後に大西洋憲章と呼ばれるものです。宣言には、「ナチスの専制政治を完全に破壊した後に、平和的かつ公正な戦後世界を建設」することが謳(うた)われています。そのためにはナチス・ドイツを打倒し、戦後は米・英が組織する国際警察力によって米英主導の世界を構想するものです。この構想実現の前提は「ナチス・ドイツの打倒」が必要であり、ならばその秘策が当然話し合われたはずです。
四 大西洋会談の密約
今、イギリスは極東で日本と対峙しており、本国はドイツの猛攻に晒され風前の灯です。何としても「ナチス・ドイツの打倒」を図り、苦境を脱出したい。チャーチルの願いは米国の参戦ただこの一点です。その秘策が話し合われたのか否か。それは、帰国したチャーチルの態度を見ればわかります。帰国したチャーチルは、「自信のために、はちきれそうに見え、有り余るほどの確信をもってイギリス国民に二本の指で「勝利のV印」をして見せたのでした(シャーウッド前掲書三九六―三九七頁)。
チャーチルの「勝利のV印」の意味が、次の資料によってわかります。
資料
大西洋会談以来、合衆国は、たとえ自国が直接攻撃を受けなくとも、極東で戦争が起きた場合にこれに参戦し、そうして最終的な勝利を確実にするであろうという見込みが、これらの懸念を和らげてくれたように思えた。期待は現実に裏切られなかった。時が過ぎるにつれて、もし、日本が太平洋で暴れ出したとしても、わが国が単独で戦うことはないという確信は一段と深まった。 (ビーアド前掲書、三二八頁)
㈠ 資料の意義
この確信は、会談でルーズベルトから参戦の密約を引き出したからに他なりません。武器貸与法によって開けられた小さな一穴は、米英の強い絆を創り出し、それはアメリカ国民との堅き誓約をも破るのです。この密約こそチャーチルが最も手にしたかった保障であり、命がけで大西洋を渡った真意だったのです。
㈡ 解説真珠湾攻撃後間もない一九四二年一月二十七日の英国下院の演説で、チャーチル自身がこの密約を暴露し、白日の下に晒しました(ビーアド前掲書、三二九頁)。
チャーチルは、首相就任前からルーズベルトとの秘密往復書簡を交わし(第十回)、米英不可分の関係を築き、武器貸与法案を考案しました。アメリカは同法案を成立させて、参戦一歩手前までの援助を可能にし、アメリカとイギリスは「非公式の裡(うち)に完全な攻守同盟」の関係となっていたのです。
一九四一年一月、米英陸海軍は第一回幕僚会議で、大西洋・太平洋の戦争において米英軍が、他の同盟国軍とともに、日独伊の枢軸国を打ち負かすための協調計画(ABC―一)を完成させます。四月には、オランダ(蘭)を加えた米英蘭の第二回目の幕僚会議が開かれました。ここでは、日本がアジアの米英蘭の領土を攻撃した場合の軍事的対抗措置が検討されました(ビーアド前掲書、六〇四―六〇五頁)。
このように日独等の枢軸国との全面戦争を想起した戦争計画が、米英蘭と共に一九四一年春には立案されていました。アメリカの参戦準備は整っていたといえます。この計画をルーズベルトは「公式ではないが」、承認していたのです(ビーアド前掲書、六五四頁)。
大西洋会談は、これらの戦争準備計画と独ソ開戦により日独両国はもはや米英の敵ではない、との見通しの上に立って行われた訳です。だからこそ米英両国は、戦後の世界支配構想にまで踏み込んで話し合うことが出来たのです。構想実現には、米英の勝利が必要です。その勝利を獲得するには、アメリカの参戦なくしてはあり得ません。
大西洋会談は、世界の諸問題を討議したのですが、その焦点は、あくまでも「アメリカの参戦」にあり、それに関するルーズベルトとチャーチルの主張の具体的調整が、主要三議題(対日並行宣言、アゾレフ群島占領、大西洋憲章)を巡って行われたのです(山岡貞次郎(井星英氏)『大東亜戦争』二〇六頁)。
「アメリカは攻撃されなくとも参戦する」。大西洋会談は、参戦への道を大きく切り拓き、大東亜戦争への歩みを飛躍的に前進させた重大事であったのです。