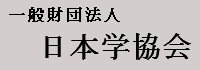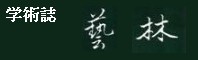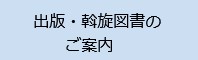『日本』令和7年正月号
歴史に学び美徳を世界へ
仲田昭一 /水戸史学会理事
新年を寿ぐ
令和七年乙巳(きのとみ)、皇紀二千六百八十五年の新春は明けた。地域の鎮守を清め、注連縄(しめなわ)を張り、清浄な結界として元朝(がんちょう)参りの人々を迎へる。各家では、門口に国旗を掲げ、ささやかながらも門松を立てて新年を祝ふ風習は、まだ健全であると信じたい。
朝日影(あさひかげ)豊栄(とよさか)のぼる ひのもとの やまとの国の春のあけぼの 佐久良東雄
春にあけて 先(ま)ず看(み)る書(ふみ)も 天地(あめつち)の 始めの時と 読みいづるかな 橘 曙覧
これらは、みな新しき年の訪れを祝ひ、佳(よ)き一年であることへの期待と決意の表明でもある。そして明治天皇の御製
あさみどり 澄みわたりたる 大空の ひろきをおのが こころともがな
を拝しては、自らもかくありたいと願ひ、祈りをも込め、明日へと向かふところである。
昭和時代の回顧
加へて今年は、昭和百年に当たり、大東亜戦争敗戦後八十年を迎へる年でもある。実に感慨新たなものがある。
激動の昭和時代を考へるに、克服すべき課題は「敗戦の再考と超克」である。その前提として、開戦の背景にある明治時代以降の大陸政策と満洲問題への考察、歴史観の確認である。幕末の開国から明治維新を経て、新政府は対外問題が新たな重要課題となつた。英国、米国、露国はもちろんであるが、ことに隣国朝鮮と清国との関係が複雑、深刻となつていつた。
多くの国民の中に流れる「なぜ、半島や大陸へ進出していくことになつたのか」の疑念。この「侵略感」が抱かれる日本と朝鮮半島および満洲、支那大陸との関係を再検討することは、日本人が敗戦の後遺症から脱却する上で必須のことと考へる。ただ、その際に、日本人が他民族の地に入り共存をはかることの難しさ、優劣感の克服の難しさは認識したい。加へて、日本国内は戦場とならなかつた。それだけに、戦争の悲惨さを本土空襲を受けるまでは深刻に受け止めなかつたことである。
一方で考へるべきことは、敗戦による占領政策が我々にとつて何を意味するかである。この再検討を通して、東京裁判史観から脱却し、自虐を正して、自主性のある真の独立国家日本の再生を期さなければならない。その際にも想ひ起すことは、昭和天皇の御製である。
昭和天皇は、戦後の混乱期の中、全国の被災地を巡幸なされ、復興にいそしむ国民を激励なされた。水戸への行幸は、昭和二十一年十一月十七、八日の両日であつた。その時にお詠みになられた御製は、翌二十二年正月の「歌会始」に披露された。 たのもしく よはあけそめぬ 水戸の町 うつつちのおとも たかくきこえて そして、敗戦に悲歎し迷ふ国民に対しては、昭和二十一年の「歌会始」で披露された御製で、 ふりつもる み雪にたへて いろかへぬ 松ぞををしき 人もかくあれ と、勇気づけられてゐた。これらのことを振り返りつつ、新たな年を踏み出したいものである。
為政者の姿勢
ところで、国内は石破茂総理大臣のもと新たな船出となつた。顧みるに、昨年後半からの政治家、特に自民党国会議員の「政治とカネ」をめぐる混迷は、見るに堪へぬものであつた。真実を語ることから逃げ、勇気を以て事実に対応し、解決を図る者がゐなかつた。責任を取る勇者は全く見られず、内外の諸問題への対応も停滞した。衆議院議員総選挙の結果、与党過半数割れも当然のことであつた。問題とされた非公認者の支部への金銭の支援も、いつの時点で為すかの判断も狂つてゐた。選挙惨敗の責任も逃れた。政治家の劣化は甚だしいものがある。自分の使命は何か、理想は何か。日々の任務遂行の責務は、厳しく問はれなければならない。少数与党の中、国策遂行への与野党議員の責任は重大である。
ここで、政治家のあるべき姿として、松平定信の例を挙げたい。天明七年(一七八七)六月、老中田沼意次(おきつぐ)の「賄賂政治」の汚濁(おだく)の世情、これを改め、理想主義にかへし、質実剛健に戻したのは新任老中の松平越中守(えっちゅうのかみ)定信、時に三十歳であつた。新政に臨んで、徳川家の祖神東照宮に祈ること毎日七、八度、或いは十度に及んだ。三河岡崎の松平家の祖廟(そびょう)にも、熱烈なる願書を認(したた)め、更に、霊巌島(れいがんじま)の吉祥天(きっしょうてん)にも願文を納めた。それには、「弊政を改めて国を救はんがためには、自分の一命は勿論、妻子の生命にかけて、必死に心願奉る、叶はずんば今の内に死を賜へ」とあつた。(平泉澄博士著『山彦』)
その任にある者の覚悟、遂行への決意と祈りに、身の引き締まる緊張を覚える。
国防の責務
世界の状況について、年を越えてもロシアとウクライナ、イスラエルとハマスとの戦争は止(や)まない。そのやうな中、昨六年十一月の米国大統領選挙で、トランプ前大統領が復権した。「アメリカファースト」を標榜(ひょうぼう)する氏は、果たしてどのやうな世界観を持ち、政策を行つていくのか、継続してゐる二件の紛争を停止させることができるのか。我々としても期待と共に重大な関心を以て対応していかなければならない。日米同盟関係は揺るがないものの、日本人としての覚悟は求められる。日米安全保障条約によつて、一旦緩急の際には米軍が支援に駆けつけることを信じて、安穏としてゐる面々もゐるやうであるが、ロシア、中国、北朝鮮が自国の防衛と称しながら日本周辺への侵出を企図してゐる。
この非情な国際環境は、冷静に判断しなければならない。戦争は誰も好むものではないが、これらの有事に身を挺して、国家の独立自存を護るのは国民の責務であることを自覚しなければならない。
占領軍発想の日本国憲法は、兵力不保持、不戦の徹底であつた。崇高な理想と冷厳な現実の対立を昇華して、国家存立のためには第九条に「一命を賭す」の一文を挿入する憲法改正を実現させねばならない。併せて、第二次世界大戦後、世界の覇者(はしゃ)となつた米国に対しては、民主主義国家を全体主義国家から護る責任を自覚し、均衡ある世界の平和の実現に努めることを切に願ふところである。
皇室の尊厳
一方で、今次の米国大統領選の姿には嫌悪感を拭へない。互いに相手を非難し罵倒(ばとう)する悪口合戦。崇高な品位と権威などは微塵(みじん)も感じとれない。敗れたハリス氏の潔さは見事であつたが、このやうな人物を大統領として戴かなければならない米国民の心情は如何なものであらうか。
そもそも、投票選挙は敵を作るものではある。かつて第二次世界大戦で赫赫(かくかく)たる戦功を挙げた米国のアイゼンハワーは、戦後コロンビア大学の学長となつたが、大統領に立候補するとき、友人の一人が「君が今のまま学長でをれば、米国市民のすべてが好感と敬意を持ち続ける。だが、大統領になれば、米国市民の半分を敵として争はなければならない」と忠告したといふ。これが選挙の現実である。
対する日本の皇室、御歴代の天皇は、「民安かれ、国平らかなれ」の祈りの毎日である。葦津珍彦(あしづなるひこ)氏が『みやびと覇権』で述べてゐる。世襲の皇子には優れた帝王学が施され、品格と気風と徳望が身に着けられる。やがて天皇となられ、仁政が施(し)かれることになる。そこには、対立ではなく「一視同仁」のお姿が現れると。皇室の尊厳は、実にここにあるといつてよい。
皇統の継承に関して、現在の「皇室典範」は男系としてゐる。しかし昨年十一月、国際連合の女性差別撤廃委員会は、これを女性差別撤廃条約の理念
「相容れない」と指摘し、改正を勧告してきた。日本歴史への重大且つ不当な侵害である。皇室の存在は日本の国柄の問題である。一般的人権論と同列に論ずべきものではない。皇統維持は日本自身の問題である。現在、提言されてゐる諸論を勘案しながら、日本人が、自らの意思で歴史を正す覚悟が問はれてゐる。
国民の美徳の回復を
様々な課題を含みながらも、永く深い歴史を重ねてきた君主国日本である。それを担つてきた国民の能力は偉大である。勤勉と誠実、忍耐と勇敢、正直と献身、また高く評価されてきた高度な技術力など、これらはみな国民の優れた美徳である。今、これらが衰微しつつあることも現実である。中でも、自動車類のリコールの増加には驚く。「技能立国日本」が泣くではないか。儲け主義や能率優先主義になり、マネーゲームに奔(はし)つて、伝統的な地道な製造力向上を疎かにしてきた結果ではないか。
少子高齢化に併せて個の自立を優先してきたことが、集団社会の崩壊を招いた。「向ふ三軒両隣」の言葉も消えようとしてゐる。
今こそ、日本のあらゆる分野の美徳を再認識して、これらを世界に弘める一年としたいものである。