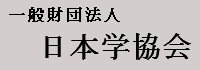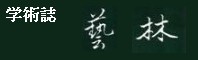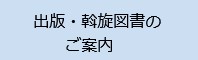『日本』令和7年正月号
歴史に見る明治人の国家観(上)
田浦雅徳 /皇學館大学名誉教授
はじめに
私は一昨年(令和五年)三月皇學館大学でのキャリアを終え、同年四月から一年間、皇學館高等学校の副校長を務めさせていただきました。皇學館大学が創立されたのが昭和三十七年で、その翌年には皇學館高校が創立されます。当時は戦後のベビーブームで誕生した子供たちが、ちょうど十五歳にさしかかるころで、高校の増設が社会的急務であり、かてて加えて日教組による戦後教育の問題が深刻さを露呈しているときでしたので、「日本人らしい日本人をつくる」ことを目指して創立されたのです。
私が赴任した昨年は、時折しも皇學館高校創立六〇周年、同中学校創立四五周年の記念の年にあたりましたので、その周年記念誌を編集・作成することを私は仰せつかりました。私も、戦前の皇學館の歴史や、草創期の皇學館高校の歴史について書きました。そこで重要なことに気づいたのですが、創立時の校長や核となる主要な教員数名は平泉澄先生門下の教員でした。校長は皇學館大学教授でもあった西山徳(いさお)先生が務められましたが、西山先生は全国各地に散っていた平泉先生門下の高校教員を地方からわざわざ招(よ)ばれました。非常に情熱のある、高い見識をお持ちの、また「日本人らしい日本人をつくる」という高い志と目標を持たれていた先生方によって皇學館高校が創設されたことを知り、大変敬服いたしました。
また大学在勤時代には、橿原神宮創建百三十周年記念(橿原神宮の創建は明治二十三年)として平成二十八年より『橿原神宮史・続編』(田浦雅徳監修)の編集にあたり、同時に『神武天皇論』(清水潔監修)においては、「幕末・明治期の神武天皇論」を執筆する機会をいただきました。この二つの本は令和二年に出版されました。そこで得た知見も今日の話で触れさせていただく予定です。
明治人から我々が学ぶもの
では本論に入ります。本日、私がみなさんに申し上げたいことは、国家を背負う明治人(幕末・明治に生まれ、明治の教育を受けた人)の、事に臨んで発露された気概や矜持(きょうじ)、誇りとは、どのようなものであったか、ということであります。「事に臨んで」というのは、歴史上の何か重大な局面に際して――殊に対外的な場面で――、ということでありまして、刻々と移り行く歴史の中で、何か国家にとって重大な選択肢を迫られた場面で、その局面に立ち会った人々はどのような覚悟で、どのようなことを考えて行動したのか。それを知ることで、一日本人として、現代に生きる我々が学ぶものがあるのではないかと思うわけです。
そもそも、ひとりの日本人が、ある種の国の命運を背負って歴史の局面に立ったときに、どのように行動するかという場面で、その人は日本の国に対する責任を感じ、それを背負っていくわけですが、その背後にはその人の日本に対する気概や矜持があるはずであると思います。
ではその国家への矜持というものはどこから来るかといえば、たしかに日本の歴史や伝統あるいは文化というものへの敬意、愛着というものも必要でしょうが――これは日本好きのあるいは親日的な外国人でも持ちうるものでしょう――、しかしさらにもっとつっこんで考えれば、究極的には国家そのものへの誇りが必要でしょう。つまり皇祖神(こうそしん)である天照大神が皇孫をこの国に天下(あまくだ)したまい、初代神武天皇によって建国された日本に生まれたという自覚から来る矜持ではないで しょうか。明治人なら恐らく多くの国民が持っていたかもしれませんが、日本の国への矜持の源泉に、こうした国家観があるのだと思います。
明治維新と神武創業への回帰
私は今、「神武天皇によって建国された」ということを言いましたが、日本の歴史上、近代以前、つまり江戸時代より前において、神武天皇によって建国された国ということをだれしもが共有できていたかといえば、そうではないと思われます。国学を学んだ人々、あるいは『古事記』、『日本書紀』に何らかの形で触れ読む機会のあった人々、あるいは平田国学の様な思想を学んでいた人々、あるいは神代以来の日本の歴史を学んだり、あるいは頼山陽の『日本外史』などの歴史書を読む機会のあった人々でありましょう。いずれにしても、知識階級や文字が読める人々でなければ、なかなかそういう機会はなかったかと思われます。
そうした幕末社会の底流にある思想的気運も背景にはありますが、やはり大きな政治的きっかけとしては神武創業の始めに原(もと)づくとした王政復古の大号令の発布(慶応三年、一九六七年)によって明治の御代がひらかれたことにあると思います。その後、明治政府の施策もあり日本が初代天皇である神武天皇よって建国された国であることが、広く人々に浸透し、戦前は紀元節として、今日においては建国記念の日として我々国民に親しまれてきたのであります。
日本人の自己認識革命としての明治維新
では神武創業への回帰ということですが、それは何故に可能であったか、この問題を人々の内面史的に、そして政治的な面から考えてみたいと思います。
幕末期の平田国学の浸透について、様々な階層へその拡がりの大きさを指摘したのは、幕末維新史および明治史研究の第一人者である宮地正人氏であります。宮地氏によれば、平田篤胤の「御国(みくに)の御民(みたみ)」(「神国の神の御末(みすえ)」)論は、武士階級、村の支配層や知識階級に広く普及し、それによって信奉者たちは、江戸時代の幕藩制度、士農工商の身分秩序の中における自分の地位を自覚しながらも、他方で、「御国(神国)の御民」(神国日本にうまれた一人)として自己認識していたというのであります(宮地正人『幕末維新変革史』上ほか)。
平田篤胤の弟子たちが篤胤の講義したものを記録した『古道大意』という本がありますが、それによると「神代(かみよ)のあらまし、神の御德(みとく)の有難き所以(ゆゑん)、また御國(みくに)の神国なる謂(いはれ)、また賤(しづ)の男(を)我々に至るまでも、神の御末(みすゑ)に相違なきゆゑん」というものを弟子たちは篤胤から教えてもらっているわけです。つまり自分たち一人一人はどんなに身分が低くても「神の御末」なのだ、また建国以来日本は、「御皇統の連綿(れんめん)と、御栄(おんえ)遊ばされ」た国であると篤胤は説きます。
平田篤胤という人は、幕末の西洋思想の導入のなかでキリスト教世界に対抗するための日本神学を構築すべく格闘するわけですが、日本は「万(よろづ) の国(くに)に並ぶ国なく、物も事(わざ)も万国に優(すぐ)れてをる事」をしきりに説きます。同様にまた『霊能真柱(たまのみはしら)』では、「我が皇大御国(すめらおほみくに)は、万国(よろづのくに)の本御柱(もとつみはしら)たる御國(みくに)にして、萬物(よろづのも萬事(よろづわざ) の 万国 (よろづのくに) に卓越(すぐれ)たる元因(もとのいはれ)」であると、日本が万国にすぐれている所以(ゆえん)を力説しています。
こうした思想を学んだ人々は、江戸時代の厳しい身分秩序から、いやおうなしに規定される身分上の自己ではなく、自分を「御国の御民」とみなすことで、それから脱却する自己認識を、セルフリスペクト(自尊心)を伴って獲得したということでありましょう。
対外的な危機の進行するなかで、こういう意識が幕末期の各層の人々に浸透していき、明治人たちの心の中に広がっていったのだと思います。日本への矜持、誇り、日本人としての誇り高き自覚というものは、例えば平田国学においてはこのような思想的プロセスを経て獲得されていったのではないかと思うのです。
私は宮地氏の平田篤胤論を読みながら、明治維新とは、当時の人々の精神史、心の内面史より見れば、いわば自己認識革命だったのではないかと思うようになりました。こうした自己認識革命を行なったのは何も平田国学を通じてだけではなかったと思いますが、神国日本と自己の関係性の獲得という、一種の自己認識革命が当時の日本人一人ひとりにとっての明治維新ではなかったかと思うのであります。
維新の志士たちの中には、自己の所属する藩の政治方針と決定的に食い違って終に脱藩を選択する人たちが出てくるのでありますが、例えば、脱藩した人たちの心の帰属意識はどこにあるか、脱藩してもなお帰属すべきところは日本国であるという自覚をもっていたのではないか。脱藩はどこにも帰属しない浪人ではない。藩の一員ではないが日本という国の一員として生きるということを決断したのではないか。脱藩とはそういうことではなかったのかと思うに至りました。
孝明天皇と神武創業への回帰
もう一つの政治的な側面ですが、何故に日本は神武創業の始めにかえることができ、今日われわれが建国の古(いにしえ)を偲ぶことができるのかと言いますと、実は明治天皇の父君で、先代の天皇であられる孝明天皇のご行動によるものであるのです。このことは、いまだ十分には知られていませんので、この機会にお話させていただきたいと思います。
孝明天皇が践祚(せんそ)(天皇の位につくこと)なさった弘化三年(一八四六)ですが、この当時は鎖国政策をしく日本沿岸に外国船が頻繁に到来し、日本は迫りくる西洋列強の脅威にさらされていました。隣の清国はアヘン戦争で英国に敗れた結果、南京条約を結ばされます。
孝明天皇という方は江戸時代の天皇のなかでも、きわめて歴史意識の高い天皇でありまして、天照大神につらなる神武天皇以来の神聖な皇統をうけついでいるという、揺るぎない皇統意識・君主意識を持たれていました。そういう天皇ですので、神代以来の神国を外夷に侮らせてはいけないという強烈な危機感と同時に、国家を守る強い責任感も有しておられました。
弘化三年八月に、孝明天皇は幕府に「海防の御沙汰書」を下して、幕府に向かって海防を督励されました。政治向きのことで天皇が幕府に命令を出すのは、きわめて異例のことです。アメリカのペリーが来航するのは、嘉永六年(一八五三)ですが、天皇は不平等条約である日米修好通商条約の調印を決して許そうとされませんでした。
孝明天皇は、一方では国のために祈ることを必死に励まれます。特にペリー来航以後、国と民を守るために、伊勢神宮や京都の石清水八幡宮をはじめ皇室ゆかりの多くの神社、寺院にたびたび祈禱(きとう)や祈禳(きじょう)(外国の侮りを打ち払うために祈ること)のために勅使を派遣され、自らも御所(ごしょ)で外国船の打ち払いや国家の安寧と民の平安を祈られました。
ペリー来航のあとの嘉永六年十二月、孝明天皇は、「神武天皇畝傍(うねび)山陵のことが兼々気に懸っているが、現在御陵あたりのことはどうなっているか、御祈念し御初穂を供したい」と仰出(おおせいださ)れています。神武天皇陵御拝は、外患祈禳の重要な柱となるのですが、その当時はまだ神武天皇陵がどこにあるかもはっきりとしておらず、陵墓の痕跡(こんせき)もそれと明瞭にはされていない状態でした。その後幕府は調査を行い、橿原の畝傍山のふもとにある二つの陵墓と思しき場所から一つを、孝明天皇の勅裁によって神武天皇陵として選定することになります。孝明天皇は、なぜ神武天皇陵の確定と修補にこだわられたのでしょうか。
孝明天皇の危機感は、元寇のときの危機感と同じで、はなはだ激しいものでした。それゆえ伊勢神宮はじめ皇室ゆかりの神社・寺院への祈禱・祈禳だけではなく、歴代天皇の御霊(みたま)にも同様の祈禱・祈禳をささげようとされたのです。ところが江戸時代は蒲生君平の『山陵志』の例にもあるように、天皇の御陵は多くの場合荒廃していました。歴代の天皇の御霊に祈るためには、天皇の陵墓がきちんとされていなければならない。そこで天皇は、幕府に命じて天皇の御陵の整備・修造に着手しました(これを「文久の修陵」と言います)。中でも初代天皇である神武天皇陵の治定(じじょう)(場所をはっきりと定めること)と修造を真っ先に実行されました。文久三年(一八六三)のことです。それは歴代天皇のなかでも神武天皇陵の御霊への祈禱・祈禳を最重要視されたためだと思います。
お墓があるということは、とりもなおさずお墓に埋葬されていた人が本当に生きていたことを意味します。神武天皇陵の治定と補修とその後の祈禱は、何よりも神武天皇の実在を証しすることにも繋がるご行動でありました。私たちが今日、神武天皇いらいの歴代の天皇を戴く日本の国柄に由来する矜持、誇りをもつことができるのは、ある意味で孝明天皇のおかげだとも言い得るのです。
志士たちの神武天皇の御代への憧憬
このように孝明天皇の皇権擁護への強い御自覚と国家守護の最終責任者としての堅固な責任感が、対外問題への言及となり、必然的に幕府の政策への批判的否定的態度ともなれば、一方では対外的危機の克服を皇祖皇宗のご神霊にひたすら祈禱するというご行動となってあらわれました。それゆえ御霊を祀るべき山陵の荒廃せる現状を憂えて、山陵修復、ことに神武天皇陵の修復に執念を燃やされたのです。
そして外夷の侮りを受けまいとする必死の攘夷のご精神は、全国のいわゆる維新の志士たちの心に波及し、攘夷の行動へと発展しました。彼らは孝明天皇の御製に込められた皇祖皇宗(こうそこうそう)を思われるご軫念(しんねん)や国民を思うお気持ち、とくに外患を憂える攘夷のお心や危機感を知って、具体的行動へと時代を動かしていくことになります。ただその行動は孝明天皇の望まれぬ幕府の打倒へと発展しましたが、少なくとも志士の行動の精神的原動力の源泉が、孝明天皇の強い攘夷の精神といわゆる国体を穢してはならないとする精神にあったことは確かでありましょう。
こうした維新の志士たちの精神の根柢にあったものの一つが、神武天皇を景仰する精神です。ここで、いくつかその例を見てみたいと思います。
有馬新七
有馬新七(正義、一八二五~六二年)は薩摩藩士で、十九歳で江戸に遊学し崎門学を学んだ人物であります。弘化二年(一八四五)、京都に滞在したおり「仁孝天皇御親祭の新嘗祭を拝することを得て、深く感激した」といいます。嘉永六年のペリー来航以来の国難のなかで、国事を憂えて居ても立ってもおられず、安政三年(一八五六)、学問修行の許可を得て江戸へ出ます。その翌年に「本田某に与ふる書」で、
真木和泉守
久留米・水天宮(すいてんぐう)の祀官(しかん)であった真木和泉守(保臣、一八一三~六四年)は、尊王討幕運動の中心的推進者となりますが、「弘化四年秋に上京、孝明天皇御即位の大礼を拝観し、公卿の野宮家に出入りし、少年の日からの王政復古・尊王討幕の念願を強めた」(田中卓『維新の歌』)といいます。
佐久良東雄
佐久良東雄(一八一一~六〇年)は常陸国新治郡出身で、当初仏門に入っていましたが、水戸学の藤田東湖や会沢正志斎らと交わり、平田篤胤に入門するなどして、天保十四年(一八四三)に仏門を去って、以後江戸に出て国学の研究に専念します。弘化二年には京都にのぼり、志士たちと交わり、王政復古実現のために奔走します。佐久良東雄は多くのすぐれた長歌・短歌を詠みましたが、神武天皇景仰の念のこもった和歌も残しています。
孝明天皇の即位の大礼がおこなわれたあとを拝んで、詠んだ歌です。
宮のむかしになるよしもがな
死に変り生き反(かへ)りつゝもろともに
橿原の御代に復(か)へさゞらめや
この歌には、日本の本来の姿である神武天皇創業の御代に回帰することを願望して止まなかった、東雄の心情がみごとに吐露されています。
これら三人の志士たちの例にみられるように維新の志士たちには、いずれも神武天皇の御代への強い憧れと回帰への願望がありました。それが明治維新の内発的な原動力となったのだと思われますが、彼らとて最初からそのような精神を有したのではなく、多くの学びや体験を通じて、どこかの時点で劇的にか、あるいは緩やかにかは人それぞれでしょうが、一人ひとりの自己認識革命を遂げられたのだろうと思います。