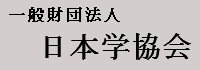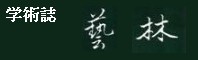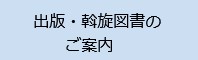『日本』令和7年8月号
わが国にとってのウクライナ紛争の教訓
廣瀬 誠 /元自衛官
ロシアとウクライナの武力紛争は、既に三年以上を経過しているが、本稿執筆時点では、依然として停戦には到っていない。ウクライナ紛争は、わが国の安全保障に数多の貴重な教訓を提示している。軍事的な視点として、一般に戦略レベルから作戦・戦術レベルまで段階がある。作戦・戦術レベルの教訓については、個々の作戦・戦闘の細部が判らないとはっきりした教訓を得るのは難しい。地域の特性、部隊の編成等の特徴や任務、指揮官の特性等多くの要素が明らかになるまでに、これから相当の期間を要すると思われる。しかし、戦略的に、わが国の防衛政策にとっての教訓を大摑みに得ることは可能であり、また、現下の激動する国際情勢において是非とも必要なことでもあろうと考える。以下、「わが国の防衛」という視点からのウクライナ紛争の教訓を概観してみたい。
ウクライナ紛争の教訓
報道を通じて知られるウクライナ紛争の一般的知識で、わが国防衛に必要な教訓を得ることはかなりの程度可能であろう。観察できるものを列挙する。
一 一九九四年、ウクライナが独立する際、当時、有数の核兵器保有国であったが、核兵器の抛棄をもってその安全を保障することについて英米露の間でブダペスト覚え書きを交換し、ウクライナの安全を保障している。そのような状況にもかかわらず、国連安全保障理事会の常任理事国であり、核大国である当のロシアの侵攻に対して、安全保障理事会は機能せず、国連の仲裁機能も期待できないことが改めて明瞭になった。
二 当初、ウクライナは「専守防衛」の戦い方をしていたが、一方的な国土への侵攻とそれによる破壊の状況は凄まじく、失った国土の奪還の努力にもかかわらず戦線は膠着(こうちゃく)する。結局、ミサイルや無人機に加えて、ロシア領への地上部隊による攻撃も一部実施するようになった。NATO諸国は、ウクライナへの部隊の派遣など武力による直接支援は控え、武器供与に尽力することになる。ロシアが繰り返す核兵器使用のほのめかしに、敵地への攻撃が核戦争に拡大することを懼(おそ)れ、支援諸国はその使用にも制限を付けた。核大国との防衛戦での各国の支援の限界が明瞭となったといえよう。各国とも当然ながら、自国の国益が優先するのである。しかし、ウクライナの強い抗戦意志があってこそ、これらの支援も行われていることは注意すべきであろう。第二次大戦でフランスがドイツに鎧袖(がいしゅう)一触(いっしょく)で敗れた後、バトル・オブ・ブリテンにおけるイギリスの「飽くまで戦い続ける」との不退転の決意と、アメリカの力強い連合国側への支援が思い起こされる。
三 核拡散防止の体制の大きな前提は、核保有国が非核国に対し核による恫喝(どうかつ)や攻撃は行わないということであろう。ロシアが非核国ウクライナに対し核使用をほのめかすのは、その前提を崩すものと考えられる。
四 映像を通じて、国土戦における民間への被害の大きさと悲惨さが鮮明となった。日常的に見られる町の姿が一瞬のうちに破壊される有様は、パレスチナにおいても同様である。現代戦における防空システムの重要性が、映像を通して誰の目にも明らかとなった。ライフラインを失った国民の生活の惨状も確認された。現代戦では、前線、後方の区別、平時、戦時の区分が曖昧となる。ドローン技術の発達は、これに拍車をかけている。
五 長期戦となり、国力が決定的な要因であることが再認識できる。ウクライナとロシアは、人口比でほぼ四倍、経済規模で概(おおむ)ね十倍の差がある。長期戦になればなるほど、戦闘員を補充し兵器を生産する能力の差は徐々に大きくなる。国力の劣る方の不利が増し、停戦協議に影響するであろう。
六 停戦協議にあたって、一般にその時の彼我の接触線が新たな境界となる。このことは、朝鮮戦争が良い例である。このため、停戦協議と並行して戦闘は継続される。緒戦で失った国土は武力によって接触線を押し返さなければ回復はできない。また、停戦協議において、中立の立場にある有力な第三国が存在しない場合、その停戦協議には困難が伴う。
七 陸続きの長い国境を持つウクライナでは、緒戦に於いて多くの避難民が国外に脱出する姿がニュースでも頻繁に見られた。四面環海のわが国では、国外への脱出は容易ではない。この点、国土戦を覚悟する以上、特別の配慮が必要となろう。
八 映像の時代において、世界を味方に付けることの可能性と重要性は明らかである。また、戦争法規の遵守については、世界環視の中にあることが判然とした。
九 NATOの東方拡大をロシアは嫌っており、プーチン大統領もそれを明らかにしてきた。一方、ウクライナはNATO加盟を強く望んでいる。力に劣る国が信頼できる同盟を得ることは重要であるが、そのために多大な努力が必要であることを再認識させられる。
わが国の視点から考える
何れの教訓も、わが国の防衛政策を考える上で貴重なものであろう。わが国では、核兵器に関することは、議論することさえ忌避されるが、核大国の核兵器使用のほのめかしは、同盟国・同志国からの支援の範囲と程度にも大きく影響することが明らかとなった。一般的な拡大抑止だけではなく、核戦力のもたらす影響についても幅広く真摯(しんし)な検討を行わなければ、世界が二つに分かれつつある現在、常任理事国かつ核大国である国々に囲まれているわが国の防衛の方途を真に探ることはできないのではなかろうか。
また、「専守防衛」の困難さについても改めて考えさせられる。「専守防衛」は、必然的に「本土決戦」すなわち国土戦となる。多くの国民が否応なく戦禍に巻き込まれる。緒戦において、侵略側は、攻撃目標はもとより、侵攻の方向や重点、兵力配分等を自主的に決めることができ、戦いの主導権を握ることができる。その奪還は容易ではない。自国民の避難等その安全を考慮した作戦は困難を極めるであろう。戦い方としては、不利が大きいのである。これらの短所を承知の上で「専守防衛」を採用するのならば、それなりの準備が必要である。現代の戦いでは、緒戦から航空撃滅戦が行われ、航空優勢の争奪戦が行われる。「専守防衛」では、奇襲を受けるリスクは高く、シェルターや警報伝達、避難計画、ライフラインの防護など国民の安全のための体制は平時から準備しておかねばならない。わが航空基地等の抗堪性(敵の攻撃から生き残ること)も最大限にする必要がある。卓越した情報能力も必要である。これらの諸準備を「専守防衛」においては完成しておかなければならない。「専守防衛」という政策を採る以上、そのために必要な諸処置が整合され一貫していなければならない。
大東亜戦争において、自存自衛、長期不敗の体制を確立した上で、米国に対してはその継戦意志を挫いて終結に持ち込むとの基本的な考え方であったはずである。しかし、真珠湾の奇襲と最後通牒の手交の遅れによって米国民に徹底的に戦う意志を固めさせることになったこと、自存自衛のための戦略物資の輸送について十分でなかったこと等を考えれば、基本とする考え方を一貫して徹底することの難しさと重要性が理解できるであろう。「専守防衛」を引き続き堅持するのであれば、そのために必要となる考え方と処置を、整合性と一貫性をもって政策体系の全領域で貫徹することが重要であることは、わが国にとって大切な視点と考える。
国のような大きな組織において、その全体像を正確に把握し、課題を正確に捉え、解決すべき問題の優先順位を適切に決めていくことは、至難の事業であり、その実現には大きなエネルギーを必要とする。その上、現代は、科学技術が発達し学問が細分化し、国家機構は巨大化するとともに各機能の分担化が進んでいる。そのような中、ただでさえ縦割りの弊害を指摘されることの多い行政機構において、国家の課題を各省庁等の所掌を超えて総合的に把握し、その解決を長期的視野で立案し、一貫した方針で全体を律する機能の必要性はますます高まっている。コロナ禍の時は、対策のため医療専門家を主体とする委員会が作られたが、コロナ禍の影響範囲はその専門分野を遥かに超えていたように思う。このような平時の不測事態はもとより、国家の活動や国民生活の全領域にその影響が及び平時戦時の境界が曖昧な現代戦の様相を考えるならば、これらのことは特に重要である。
能登の震災復興の遅れや、米不足の原因について昨年夏の発生以降長きに亘り明らかにできなかった状況など、わが国の課題解決能力が落ちていることを危惧させられる昨今の状況は、終戦直後の荒廃した国土を十年余りの期間で「もはや戦後ではない」と宣言できるまでに復活させたような国の活力も失われているように感じる。戦後八十年を迎えたが、改めて、わが国の現在地を見つめ直す時期に来ているのではなかろうか。