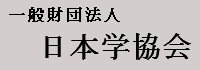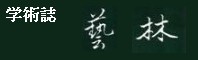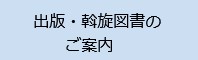『日本』令和7年8月号
巨大共産主義国の大変革(下)― 中国の大変革(その二) ―
吉田和男 京都大学名誉教授
人民解放軍の役割
人民解放軍は中華人民共和国建国の基盤であり、人民解放軍を統率する中央軍事委員会主席は中国の最高指導者でもあって、中国が軍事中心の国であることは今日でも変わらない。鄧小平後は国家主席、共産党総書記、中央軍事委員会主席は兼任されている。
大東亜戦争の後、一九五〇年に独立国であったチベットを軍事侵略で併合し、一九四八年に独立国であった東トルキスタンを侵略して新彊ウイグル自治区に収めたのには人民解放軍の役割が大きい。
また、国内の民主化運動を抑えるためにも、人民解放軍が大きな役割を果たしている。中央軍事委員会主席が最高指導者であることが中国の実態であることは、ここからも理解できる。ウイグル人等に対する人権問題では、アメリカを始め国際的な非難を浴びているが、人民解放軍の力で抑えており全く意に介していない。
中国のグローバル戦略
中国の経済成長の結果、中国は世界に勢力圏を広げようとするグローバル戦略を始める。中国が考える世界におけるグローバル戦略はアメリカとの比較においてはまだまだ大きなものとはいえない。台湾問題で台湾の併合には軍事力の使用を念頭においているが、アメリカの海軍力に対応できるまでには至っていない。
しかし、中国が九段線として示した南シナ海支配はすでに完成に近づいており、第一列島線までの制海権・制空権の獲得に努力している。さらに、太平洋の第二列島線までの制海権を狙って海軍力の増強を図っている。このため、現在、太平洋の制海権を保持しているアメリカと対立することになる。
第一列島線とは九州を起点に、沖縄・台湾・フィリピン・ボルネオ島に至るラインであり、第二列島線とは伊豆諸島を起点に、小笠原諸島・グアム・サイパン・パプアニューギニアに至るラインのことである。
これは一九九七年まで中央軍事委員会常務副主席であった劉華清が打ち出した人民解放軍内部の国防方針といわれている。劉華清副主席が掲げた海軍建設のタイムスケジュールとしては「再建期」として一九八二年から二○○○年の間に中国沿岸海域の完全な防備態勢を整備することであり、ほぼ達成済みである。
次の「躍進前期」である二○○○年から二○一○年の間に第一列島線内部の制海権を確保する。その次の「躍進後期」である二○一○年から二○二○年の間に第二列島線内部の制海権を確保する。そして、「完成期」として二○二○年から二○四○年の間にアメリカ海軍の太平洋、インド洋の独占的支配を阻止することを目標としているようである。
このスケジュールはすでに大幅に遅れているものの、中国海軍の戦略を示している。もちろん、アメリカ海軍が容認できるものではなく、「エアー・シーバトル」という作戦で対抗しようとしている。太平洋の制海権を獲得することは容易ではない。
しかし、アメリカはかつてのような大きな戦争を遂行できる能力を失っており、中東から手を引いていて、インド・太平洋における対中国戦力を相対的に強化している。
ウクライナ戦争で見られるように米露対立が今日の焦点であるが、やがて米中対立が世界的な軍事・経済両面での対立の中心となっていくことは目に見えている。
一帯一路構想
二○一三年に習近平主席が「シルクロード経済ベルト」構想を打ち出し、翌年のAPEC首脳会議で、中国から中央アジア・中東・ロシアというユーラシア大陸を経てヨーロッパに至る陸路の「陸のシルクロード」(一帯)と、中国からASEAN・南アジア・アラビア半島・アフリカ東岸・ヨーロッパに至る「海のシルクロード」(一路)の地域でインフラ整備、貿易促進、開発資金の提供などを進めようとする「一帯一路」(正式には「シルクロード経済ベルトと二十一世紀海洋シルクロード」)経済圏構想を打ち出している。中国は建国百年に当たる二○四九年までの完成を目指している。
「一帯」のシルクロード陸路では中国から中央アジアに、鉄道、パイプラインなどのインフラ整備を中心にして、その周辺地域を工業地帯とし、これを中心とする巨大経済圏を構想するものである。
鉄道では義烏・ロンドン間および義烏・マドリッド間を結ぶ路線は、中国大陸とヨーロッパを結ぶ世界最長の鉄道路線である。他にもユーラシア・ランドブリッジの浜州線や、トランス・ユーラシア・ロジスティックスが代表的であるが、これはモスクワを迂回するルートである。アゼルバイジャン・ジョージア・トルコを経由するルートも示されている。
パイプラインは、中国・カザフスタン国境から北カスピ海まで伸びている。このパイプラインで中央アジアの油田やガス田から中国へ石油・天然ガスを送れるようになる。
中国は「一帯」の中核地域となる中央アジアのカザフスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタンには巨額の投融資を既に行っており、経済的関係を強めている。また、タジキスタンには人民解放軍の軍事基地があるといわれている。
「一路」の海のシルクロードでは、主要な港湾建設などのインフラ投資を行うことで、海路による巨大経済圏の建設を目指すとしている。
構想されている福建省・カンボジア・スリランカ・モルディブ・パキスタン・イラン・ジブチ・ローマまでの海廊のチェーンは、インド大陸を人の顔に見立て、「真珠の首飾り」と呼ばれている。これらの拠点国には多額の経済援助を行っている。
スリランカでは中国の支援で行われたインフラ建設で赤字が続き、国家破綻を起こしている。借款の棒引きのために、ハンバントタ港の二〇一七年より九十九年間の運営権を、中国国有企業の中国港湾控股有限公司が買い取っており、それの軍事利用も指摘されている。これによって、アデン湾からインド洋をマラッカ海峡に向かう位置に、中国海軍が拠点を持つことになる。このように中国は、「海のシルクロード」の要衝を抑えつつある。
この他、北極圏まわりで欧州・ロシア・日本・中国を結ぶ「氷上のシルクロード」や太平洋を経由して南米横断鉄道で中南米諸国を結ぶ「太平洋海上シルクロード」の構想もある。これは太平洋の制海権とも絡んでおり、ソロモン諸島などの太平洋諸島への援助を行っている。中国は上記の他、ギリシャ、イスラエル、モロッコ、スペイン、ベルギー、コートジボワール、エジプト、パナマなど世界各地で、港湾建設・利用権の獲得を推し進めている。
この構想実現のための鉄道・高速道路整備や港湾整備などのインフラ投資計画は、史上最大の一兆ドルになるのではと言われている。このために、二〇一五年に中国が主導してAIIB(アジアインフラ投資銀行)が設立されている。ここには中国以外にも、インド、ロシア、イギリス、フランス、ドイツなど百三ヶ国が出資している。これは世界銀行やアジア開発銀行が出資・融資を行っていない事業を中心とし、これらを補完するものとしている。しかし、重要な投融資では競合も避けられないであろう。
さらに、二○一四年に設立されたシルクロード基金(中国独自のファンドであり、四百億ドルに及ぶとされている)などの資金で開発途上国へのインフラ建設の援助を行うとしている。これらを通じて人民「元」の国際通貨圏の構築などの世界的規模での中国経済圏の構築を目指している。
すでに、「一帯一路」構想には百四十六ヶ国が関連しており、二○二三年時点で、EU十六ヶ国を含め百三十一ヶ国、三十二の国際組織が協力文書に調印をしている。中国はたびたび首脳級を含めた国際フォーラムを開き、世界各国に協力を呼びかけている。
しかし、これらも関連地域の経済発展というよりも、中国の勢力圏の拡大を目指すものでしかないのも事実であろう。世界銀行やアジア開発銀行が手を出さなかった投融資対象は、必然的にリスクの高いものにならざるをえない。また、世界銀行やアジア開発銀行の投融資が嫌われるのは、厳しいコンディショナリティ(条件)が課されるためである。しかし、AIIBなどの投融資が中国の政策的判断としてコンディショナリティを課さなければ、投融資を受ける方からは歓迎されるのは当然のことである。しかし、これは事業の成功可能性を低下させることになる。スリランカ、ラオス、マレーシア、パキスタンなど多数の国で債務問題を起こしており、厳しい目で見てゆかざるをえない。
AIIBなどの投融資が不良債権となるリスクがあり、最悪の場合、投融資先が国家破綻となった時に、政治的・軍事的に解決しようとすれば、レーニンの『帝国主義論』を実際に行うことになる。AIIBは中国のグローバル戦略の一環にすぎない。公的国際金融機関として健全な金融業務が行えるかどうかには不安が残る。不良債権が拡大したときの準備が必要である。不良債権となれば中国による政治的解決しかない。
一帯一路構想が成功するには、乗り越えなければならない問題が山のようにある。しかし、今のところ中国のグローバル戦略に沿って資金のバラマキを行っており、問題が生じるのはこれからである。
中国の将来
中国は経済力では既にアメリカに近づきつつあるが、いくつかの難関を抱えている。二○○○年から二○一九年までは六%から一四%の高い成長率で推移してきたが二○二○年には新型コロナウイルスに対するゼロコロナ政策で、経済成長率は二・三%に下落する。
二○二一年には反動で八・三%となるが、不動産バブル崩壊により恒大集団が負債三十兆円以上を抱え、資金繰りに行き詰まり、デフォルト危機の問題が表面化した。他の不動産大手も次々に経営難が表面化している。
このため二○二二年には不動産販売が低迷して住宅価格が下落し、不良債権が増加し、地方政府の財政問題、銀行破綻や金融不安が発生するというバブル崩壊現象から経済成長率は三%まで低下する。
二○二三年は五・四%になるが二○二四年は四・八%と見込まれている。IMFは中期的には経済成長率がさらに低下し、二○二八年には約三・五%になると予測している。政府は種々の支援策を打ち出しているが、根本的な解決にはなっておらず、中国経済は減速傾向にある。特に、若年層の失業率の上昇が深刻な問題となっている。二○二五年六月の、十六歳から二十四歳の若年失業率は一四・五%になっている。また、トランプの対中高関税に対して報復措置を取っており、中国経済にとってはマイナス材料である。
しかし、人口が十四億人であり、しかも先端技術においても急速にキャッチアップしている。まだまだ貧困層が多く、経済成長に対する熱意も高い。現在の経済上の問題をすり抜けることができれば、経済成長の潜在力は高い。
中国が経済統制をどの程度にするかが問題であるが、習近平主席が経済発展の芽を摘むような経済統制をかけてくるとは思えない。
政治的には台湾問題が最大の問題点である。近年、海軍力を強化し、西太平洋の制海権を獲得することを目指している。そして、台湾周辺で大規模な軍事演習を行い、圧力をかけている。しかし、中国には現段階ではアメリカと台湾問題で戦争を起こす力はない。そのため軍事力の増強に努めている。核兵器についても現在の四百発強程度のものを二〇三五年までに千五百発体制とするために増産している。
習近平主席の最大の課題は、独裁政治の基礎となっている中国共産党への支配力の維持であるのは間違いないであろう。しかし、腐敗政治撲滅運動などで追放されたかつての共産党主流派の中国共産党青年団出身者などが、黙って指をくわえているとも思えない。さらに共産党内の統制力低下も懸念されている。
経済成長によって力を持ってきたアリババやテンセントなどの新興の民間大企業に対して、既に統制を強化しており、現在は抑圧されている民主化勢力への統制も強化されるであろう。民主化の抑制、ネットの規制、言論統制などの統制をどこまで行うかも重要な視点となってくる。
中国のグローバル戦略にも不確定要素は少なくない。「一帯」で旧ソ連の一部であった中央アジア諸国が中国の勢力圏内に入ることとなれば、現在はウクライナ問題で露中間関係は強化されようとしているが、ロシアが黙っているとは思えない。また、「一路」においても世界の制海権を持っているアメリカと中国の対立を生むことになりかねない。米中露は核保有国であり、軍事大国である。
日本の対応
日本はロシアと中国の隣国であり、太平洋を挟んでアメリカとも距離は遠いが隣国である。三ヶ国とも第二次世界大戦では戦火を交えた国であった。敗戦によりアメリカの占領下に置かれ、講和後も日米安全保障条約で同盟国となり強い結びつきの国となる。そして、日本は戦後のパックス=アメリカーナにおいて大きな恩恵を受けて、経済大国となった。
その同盟関係を作らせてきたのがソ連であった。ソ連の崩壊を受けて、ロシアと日本は北方領土の問題はあるものの貿易は拡大し、サハリンの油田・ガス田の共同開発などが行われるようになり、関係は改善した。しかし、ロシアは北方領土返還に応じようとせず、軍事基地化を進めている。現在はウクライナ戦争に対する経済制裁を行っており、関係は冷え込んでいる。
中国とは一九七二年に国交正常化を行い、戦後賠償に代えて巨額の経済援助を行って中国経済を支えた。改革開放政策により日中貿易関係は拡大し、対中投資も盛んに行われ、日中経済関係はウィンウィン関係にあり、強固なものとなっている。しかし、尖閣列島領海への侵入もあり、日中対立の恐れもある。
また、米中は台湾問題や貿易摩擦で対立するとともに、先に述べたように中国のグローバル戦略で対立する可能性もある。米ソ対立の次は米中対立であるといわれており、日本が米中対立の防波堤になる危険性は十分にある。そうなれば最悪である。しかも、アメリカもパックス=アメリカーナからアメリカ・ファーストに軸足を移しており、日本も日米安保条約へのただ乗りは許されなくなっている。
ロシア及び中国という核保有の独裁国家とも、隣国として付き合って行かざるを得ない。日本はいち早くゼロ成長経済から脱却して、独自の外交力・防衛力強化などで自らの国力の増強に努めなければならない。