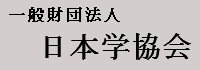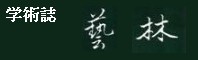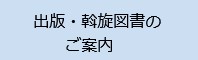『日本』令和7年9月号
不安の時代を生きる
植村和秀 /京都産業大学教授
不安にどう対処するかが、現代の課題なのではないか。もちろん、不安はいつの時代にもあった。不満もいつの時代にもあった。人間は、不安を持つ生き物、不満の出やすい生き物である。
それでは、現代の特徴とは何であろうか。芥川龍之介は「或る旧友へ送る手記」で、「何か僕の将来に対する唯ぼんやりした不安」と書き記している。昭和二年に亡くなった後に見つかった遺書の一節である。
しかし、現代の不安はぼんやりとはしていない。むしろ、はっきりとしすぎているように思われる。つまり、現実に根拠のある不安、確定的に見える未来があるからこその不安である。しかもそれは、日本だけで感じられるものではなく、世界各地同時進行で感じられているのではないだろうか。
もっとも、現実に根拠があるのであれば、不満と呼ぶことも可能なのかもしれない。不安と不満は重なり合うところがある。未来への不安が現在の不満につながり、現在の不満が未来の不安につながるのは、自然なことである。ところが現代の不安は、不満を感じてもどうにもならない所に原因を有している。はっきりしているのに、どうにもならない。これが現代の不安の特徴である。
日本に生きる不安
この問題について、もっと具体的に検討してみよう。日本の現在の国家的課題は少子高齢化である。もちろん、少子化によって人手不足が心配され、就職状況が好転するなど、若い世代にとって有利な現象も起きている。他方、年金制度や医療制度、介護制度などの持続可能性が憂慮され、若い世代には特に重大事である。しかし、課題ははっきりしているのに、どうにもならない。大規模な移民受け入れに踏み切るならともかく、そうでなければこの事態を受け入れるしかない。少子高齢化は確定した未来であり、日本の未来への懸念は現実に根拠のある不安である。
この少子高齢化への不安は、地方の衰退への不安に連動する。東京一極集中は是正されず、都会への人口流出は止まらない。若い世代の流出、優秀な人材の流出は、県まるごとの衰退さえ心配させる規模となっている。しかもそれは、農村の衰退への不安とも連動する。日本の国柄を形成してきた米づくり、日本の原風景として愛されてきた農村風景の行く末を心配するのも、現実に根拠のある不安のためである。近年高まっている食糧安全保障への心配も、戦争の懸念のみならず、農村の未来への懸念にも由来しているのであろう。
これに対して安全保障への関心の高まりは、とりわけ国際事情に後押しされたものである。ロシアも北朝鮮も中国も、何をするか分からない。現時点で日本は戦争の渦中に入っていないものの、そのすぐ隣に立っていることは明らかである。外交や安全保障に関する不安も、現実に根拠のある不安である。
しかし、これまで述べてきた問題よりも、さらに根本的なのは皇室の未来という問題である。明治維新を根本的に支え、昭和の敗戦にも耐え抜いた皇室がどうなるのかは、日本の根本に対する不安となる。つまり現在の日本にある不安は、根本的かつ全体的なものなのである。
現代に生きる不安
とはいえ、不安を感じる状況は日本だけのものではない。世界各地でも、現実に根拠のある不安は高まっている。まず根本的なものとして、地球の未来に対する不安がある。異常気象は日本だけではなく、世界の至る所で生じている。他方、地球規模での人口の激増は、食糧や資源の未来に深刻な不安をもたらしている。いずれも根本的かつ全体的な問題であり、現実に根拠のある不安である。
さらにまた、人間の生活のあり方の変化にも不安は由来している。ソ連滅亡以後のグローバル化と情報化の急進展は、われわれの生活を日々変化させ、その変化に追いつくことが、通常の生活を営むために必要となっている。それはまた、あたふたと、考える余裕もなく変化にあおられる生活、とりわけ、情報通信技術の発展にあおられる生活でもある。
もちろん、歴史的な変動期に生きる人間は、いつでもそのような状況を生き、時に活用もしてきた。明治をたくましく生きた人たちも、そうだったのであろう。それでも、自分が主導権を持って生活を構築できていない実感は、変化に追いつけない人間、追いつくので必死な人間の不安を強くかき立てる。今後も追いつけるのか、追いつけなくても生活していけるのか、という不安である。
夏目漱石は「現代日本の開化」という明治四十四年の講演で、「涙を呑んで上滑(うわすべ)りに滑つて行かなければならない」と述べている。西洋由来の文明開化は、日本では「皮相上滑りの開化」にならざるをえない。しかし、それを直視して生きていくしかない、との主張である。
ただし、われわれの現代の開化は、世界同時進行の変化である。漱石にとっての現代との違いは、そこにある。しかも現在の日本であれば、変化の有力な牽引者となる実力はあるはずである。もっとも、自分は取り残されるかもしれないとの不安は、それで解消できるものでもない。
政治家の課題
このような時代において、指導的な政治家に求められるものは何であろうか。それは何よりもまず、多くの人に安心感を与えることなのではないか。安倍晋三首相が支持を集めたのは、個別の政策への評価のみならず、安心感を与えることに徹底していたからではないだろうか。不安な時代だからこそ、不満に思う問題の解決も重要ではある。しかし、根本的かつ全体的に安心感を与えてくれる政治家を、国民は求めていたのではないか。
もちろん、そこには危険性もある。現実に根拠のある不安に応えて、根拠のない安心を与えることはむしろ有害である。トランプ大統領はアメリカ国内の安心を最優先し、国外で多くの人びとの不安をかき立てている。しかし、現代の政治課題は以前よりもはるかに複雑である。また、政治に参加する人の数は、以前よりもおそらく増えている。政治課題は地球規模で複雑に連動し、何かを決定した際の影響を読み通すことは難しい。インターネット上での意見表明も政治参加の一つの形であり、その実行への心理的なハードルは、すでにかなり低い。以前よりもはるかに難しい問題に取り組み、以前よりもはるかに多くの人びとと相対する。現代の政治家に求められていることは、それにもかかわらず現実に根拠のある安心感を与えることであろう。トランプ大統領が与える安心は、本当に現実に根拠のあるものなのだろうか。
一時的な安心感を与えることに甘んじず、確定的に見える未来に明るさを示し、根本的かつ全体的な不安に応える。はっきりしているのに、どうにもならない。そこで未来に向かって共に歩んでいく姿勢を示すことが、先人から引き継いできた日本国家を担う現代の指導的政治家の使命なのではないか。しかもそれは、日本のみならず世界各地でも求められる現代の政治家の姿ではないかと思うのである。