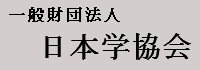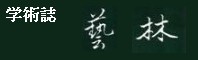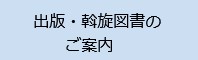『日本』令和6年3月号
教師が尊敬される社会の回復を
渡邉規矩郎 /元教育記者・教育研究者
教育界は教師不足が深刻で、教師の魅力をさらに高め、優秀な人材を教育現場に集めることが急務になっている。このため国は、働き方改革、処遇の改善、学校の指導・運営体制の充実、魅力向上について一体的に取り組むというが、これらは長年検討され続けてきた課題だけに解決は容易ではない。
教師が学校から去っていく
学校現場が長時間労働によるブラックな職場といわれて久しいが、文部科学省の調査によると、公立学校教師のうつ病など精神疾患による休職者数は、平成十九年度から毎年五千人前後で推移しており、昨年度は六千五百三十九人と、前年度から六百四十二人増加しこれまでの最多となった。その原因は、 ①増加する一方の雑務②難しさを増す学級経営③保護者対応④複雑化する職場の人間関係、という「教師を取り巻く四重苦」の中で勤務を続けた結果とされる。
筆者の身近でも、大学の教え子がドクターストップで教壇を去って行った。教育への夢と志を持って教職に就き、現場でも若手のホープとして期待され、生き生きとした姿を見せていたが、数年後、大規模校からへき地小規模校に異動後しばらくして、教師を辞めて転職するとの連絡を受けて驚いた。結論を出す前に相談に乗ってやれなかったことを悔やんだが、あとのまつりだった。
教師が辞めれば学校に欠員が出る。文部科学省の調査では、令和三年五月の時点で、全国の公立の小中学校や高校などで二千人余りの教師が不足していた。全国公立学校教頭会が昨年夏、令和四年度間の教師の不足状況を調べたところ、約二割の小中学校で欠員があり、教員未配置の小学校のうち三割の学校で副校長・教頭が担任の代わりの業務をしていた。
昨年四月の教員勤務実態調査で、「過労死ライン」と言われる残業時間が月八十時間に相当する可能性がある教員が中学校でおよそ三分の一を占めている過酷な職場環境を嫌って、学生の教師志願離れにも歯止めがかからない。文部科学省の集計によると、令和五年度教員採用選考の全体倍率は三・四倍と過去最低。小学校では二・三倍と特に低かった。大量退職者に伴う採用者数の増加と既卒の受験数の減少が影響したため、多くの自治体では教員確保に向けて、民間や企業の教職経験者を対象にした秋選考、教員採用試験の早期化や複数回実施など選考の見直しが進むとみられる。
教師確保にむけた中教審の検討
学校現場での教師不足や長時間労働が深刻化するなか、中央教育審議会(中教審)は昨年五月以来、「『令和の日本型学校教育』を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について」の審議を重ねており、今年春ごろをめどに一定の方向性を示すことにしている。具体的な処遇改善策としては、教師には残業代が出ない代わりに給料月額の四%が一律支給されている教職調整額の引き上げや、中学校の三十五人学級の実現などが議論されている。
中教審の方向づけを受けながら、文部科学省は新たな施策を進めることになるが、同省は、教師の確保に向けて、教師として働くことを希望する社会人を対象に各都道府県の教育委員会が行う研修、いわゆる「ペーパーティーチャー研修」や、特定の地域で教師を目指す学生を募る大学の「地域枠」の設置などについて、本格的に財政支援することにしている。このほか「特別免許状」の活用は、特に地方自治体において有効な手立ての一つという。これらは教師不足の解消のみならず、学校教育の多様化や活性化、専門性の向上に資するものだとしている。
教師の資質向上策としては「百年河清を待つ」に等しいと批判されるかもしれないが、とにかく、国や自治体は、教師が学校現場で安んじて教育を行える環境・条件整備には努めてもらいたい。
AI時代にこそ必要になる力
教師不足の問題の一方で、学校や教師を取り巻く環境は、大きな変化が待ち受けている。それは社会の在り方が劇的に変わる「ソサエティ5の時代」(情報社会に続く超スマートな社会)」、先行き不透明・予測困難な時代の到来。加えて、二〇五〇年には、生産年齢人口が現在の約四分の三に減少、今後十年間で公立小中学校の児童生徒数が約一割減少する。また、特別支援教育の対象となる児童生徒や外国人児童生徒・不登校児童生徒の増加、児童虐待、ヤングケアラー、貧困など、子供の抱える困難の多様化・複雑化が予測される。さらに「GIGAスクール構想」による一人一台端末環境の実現、デジタル技術とデータを活用した知見の共有と新たな教育価値の創出の必要性に迫られる。
AI時代の到来を「黒船」と受け止め、ピンチをチャンスにしてほしいと願うのは、平成二十年、二十九年の学習指導要領改訂の当事者だった合田哲雄文化庁次長。同氏は『日本教育新聞』の新春対談(一月十五日付)で、「AI時代に必要な四つの力」を次のように指摘していた。
一つ目は、AIへのチェック機能。生成AIが提示した文章・テキストなどに対して、直観的におかしいと感じるセンス。これには知識がなければならない。
二つ目は、自分で問いを立てる力。AIのように与えられた問いに瞬時に答えられることよりも、仮説や問いを立てることが大事になってくる。
三つ目は、身体感覚。触覚、視覚、嗅覚、聴覚などを通して、人間はそれを言語化し、知性に昇華するが、これはAIには絶対できない。
四つ目は、対話の中で知性を生み出す。互いに言葉を交わす、その間に知性が立ち上がる。知性は頭の中に閉じ込めておくものではなくて、対話の中で磨かれる。これもAIにはできない。
合田氏によると、この「AI時代に必要な四つの力は、前々回、前回の学習指導要領改訂でも議論された内容だが、「四つの力の育成を、GIGAスクール構想で一人一台端末になった次期学習指導要領でこそ実現させたい」と述べていた。
教師は専門職、誇りを持って
「AI時代に必要な四つの力」はとりわけ目新しいものではない。従来から日本の教育が大事にしてきたもののはずだ。知・徳・体をバランスよく育む全人的な教育を重視する日本型学校教育は、国際的にも評価が高い。その点で日本の教師は自信を持ってよい。AI時代の到来だからといって別に浮足立つ必要はない。あらためて、地に足をつけた研究実践こそが大切になってくる。
その際、肝要なことは、教師は教育の専門書以外の書物を読み、様々な体験を積むこと。不確実な時代だからこそ、確実なものである歴史と伝統文化の本質を学び継承し、次代を担う子供たちに引き継いでいく使命がある。その中から、教師は専門職であるという誇りが芽生える。子供たちの奥底にあるものを引き出し、それを共有することができるのは教師にしかできない仕事であり、教師の出番である。
教師が誇りを持てば、社会から教師が尊敬される。そこに教師離れなど起きるはずがない。
AI時代に必要な教育技術はもちろん必要だが、それ以前に人間力を高めることが何より肝要だ。それには、自己啓発・自己研鑽以外に道はない。