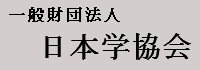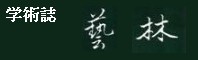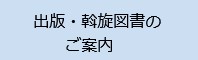『日本』令和7年3月号
桜の餘香(三)― 英霊未だ嘗(かつ)て泯(ほろ)びず
片山利子 /作家
「湊川だよ」
「湊川だよ」。第七二一海軍航空隊(雷神(じんらい)部隊)飛行隊長・野中五郎少佐(戦死後大佐)が、昭和二十年三月二十一日、第一神風桜花特別攻撃隊を率いて出撃する際、海兵同期(六十期)の金子義郎(ぎろう)少佐に小声で遺された言葉です。
この攻撃は、一式陸上攻撃機(一式陸攻)の腹に滑空機「桜花」を懸吊して目標近くまで飛び、発射させ、その後は「桜花」搭乗員の操縦で突入するというものです。

この日が初陣でした。
同月十八日から二十日まで、ウルシー環礁(九州最南端から二千三百キロ。米軍の大泊地)を発した米機動部隊第五十八任務部隊が九州、瀬戸内海に侵攻、敵艦載機と我が第五航空艦隊との激しい航空戦が繰り返され、防空戦による戦闘機の消耗は甚大でした。
二十日、第五航空艦隊司令長官・宇垣纏 (まとめ)中将(海兵四十期)は、南下中の任務群を探知し触接を続けているとの報告を受け、南西諸島線の警戒とその速力に鑑み、桜花隊に攻撃の準備を下令。翌二十一日、早朝索敵の結果、任務群を都井岬(といみさき)の先に発見との報告に、天候、任務群の状況から、待機中の桜花隊に出撃を命じたのでした。
桜花隊では、神雷部隊司令・岡村基春大佐(海兵五十期)、野中少佐らが、直掩機(ちょくえんき)の不足もあり、この作戦には猛烈に反対したのですが、宇垣長官は「この機を逃せば、遠くウルシーに梓隊の遠征を余儀なくされ、しかも成功の見込みは薄い」と決断したのです(梓隊とは鹿屋を作戦基地とする最初の特攻隊・梓特別攻撃隊のことで、十一日鹿屋基地を出撃する際、手違いなどもあり、宇垣長官は苦い思いを抱いておりました)。直掩機の予定は五十五機。それでも少な過ぎるのに、三十一機しか出せなくなり、心配は募ります。それでも見送りの際には、心配を隠せない岡村司令を激励しました。その岡村司令は野中少佐に「今日は俺が征く!」と言うのですが、「司令の出る幕ではありません。そんなに自分が信用できないのですかっ!」と強い口調で断わられたといわれております。
このような経緯で、桜花隊特攻の出撃を迎えたのでした。
作戦成功の見込みのない命令に反論をしながらも受け入れられないと知るや従容として出撃したのです。
野中少佐にとって、これはまさに「湊川」だったのです。しかしそれは、負け戦に出るという、絶望や諦念の「湊川」では決してなかったはずです。なぜなら、野中少佐は読書家で、『太平記』は愛読書の一冊だったからです。
『太平記』の記述による湊川の合戦
では楠木正成はどのような思いで湊川に向かい、奮戦し、殉節(自決)されたのでしょうか。
『太平記』には、湊川の合戦について次のように記されています。
鎌倉幕府滅亡・中先代の乱を経て、新田義貞と足利高氏の対立が深まり、高氏の謀反の野望も明らかになります。
後醍醐天皇は、尊良(たかよし)親王を征夷大将軍に、新田義貞を総指揮官に命じて、高氏討伐の軍を起こされます。一度は足利勢に圧倒されて、負け戦が続き、後醍醐天皇は難を逃れて都から比叡山に行幸されます。
直後、都に入った義貞と陸奥から到着した北畠顕家が力を併せて足利方の軍勢を破り、足利勢は九州に落ち延びました。
九州で力を蓄えた高氏は、再び京を目指して攻め上ってきます。安芸の国(現広島県)厳島に到着した高氏は、持明院光厳(こうごん)上皇の院宣(いんぜん)を賜り出発、鞆(とも)の浦(現広島県福山市鞆町鞆の浦。古来、瀬戸内海の海運にとり要衝の地)で、軍勢を海陸二手(ふたて)に分けます。海は高氏が総指揮官として兵船七千五百余隻、陸は弟直義(ただよし)を総大将に二十万騎と配置を定めて、京を攻め落とそうと進んできます。
義貞は陣を兵庫に引き、この軍勢を迎え討つ計画を立てます。正成は、朝廷に呼び出され、義貞と力を併せて足利軍を防ぎ止めるよう勅命を賜ります。
しかしながらこの情勢を見るに、あまりにも味方に不利。正成は、一端義貞を呼び戻し、天皇をお守りさせて比叡山にお移り願い、その後、比叡山から義貞が、淀川の河口から正成が、高氏を挟撃(きょうげき)することで勝利に導くという策を奏上します。天皇をはじめ、人々もそれに賛成しますが、ひとり坊門清忠だけは「足利討伐のために朝廷から差し下したのに一戦も交えぬうちに戻れとは、また再び比叡山に臨幸とは、天皇を軽んじたるものであり、官軍の道を失うことである」と激しく反論します。正成は「戦いを知らぬ素人」とは思いますが、それ以上反論はせず、兵庫へ下りました。
兵庫に着いた正成は、義貞と酒を酌み交わし、坊門清忠と作戦について齟齬(そご)があったことを打ち明け、死を決した二人は腹を割って語り合います。
新田義貞は和田岬(現神戸市兵庫区。大阪湾・神戸港に面した岬。この岬が南西風と潮流を防ぐためその北東側が天然の良港となっている)を本陣とし、経島(きょうのしま)(大輪田泊・現神戸港)には義貞の弟脇屋義助を、灯爐堂(とうろどう)(和田岬の南)の南の浜には大館氏明を配し、さらに須磨口には、中院定平(なかのいんさだひら)、菊池武重ら諸将も参戦しました。
楠木正成は湊川の西側にある会下山(えげやま)に布陣します。
須磨の上野、鹿松丘(まつのおか)、鵯越 (ひよどりごえ)の辺りには陸路を攻め寄せてくる足利直義の大軍が見えます。戦が始まり、経島付近にいた高氏軍が一斉に上陸を開始します。新田・楠木軍はそれを阻止し、上陸不能と判断した高氏軍は、海岸沿いに東に移動し始めます。高氏軍は和田岬の近くまで漕ぎ寄せ、一気に上陸しましたので、新田軍と楠木軍は割り込まれた形となり、 連絡が取れなくなりました。
『太平記』には、直義の軍と戦う正成、正季兄弟は「七度合(ななたびあ)ひ、七度分(わか)る」とあります。その心は、ひとえに、直義に近づき、二人で組んで討ち果たそうというところにあるというのです。
正成と正季は奮戦し、五十万騎の大将・直義を追い詰め、いざ討たんとした時、薬師寺十郎次郎が駆けつけ、直義を救ってしまいます。

六時間の合戦で、楠木軍は十六回敵軍に突撃を繰り返し、七百余騎の軍勢は僅か七十三騎になってしまいました。近くの民家に入り、腹を切ろうと鎧を脱ぐと、正成は十一か所もの切り傷を負い、他の者たちも負傷していました。もはやこれまでと切腹を決した正成は正季に「最期の一念は」と尋ねます。正季は「七たび人間に生まれて朝敵を滅ぼしたいものと思います」と答えます。正成は嬉しそうな様子で「この兄も同じ心だ」と言いながら刺し違えて斃(たお)れました。七十一人の家臣も腹搔(か)き切って続きます。
兄菊池武重の使いで須磨口の戦いの様子を見に来て、この場面に出会った菊池武吉も、逃れようとすれば逃れられたものを、行を共にしたのでした。
菊池氏もまた勤王の家系です。元弘の乱の論功行賞の折、楠木正成は自らの功績は語らず、勅諚(ちょくじょう)(天皇の仰せ)により落命した菊池武時を忠厚(功)第一とすべきと論じ、後醍醐天皇は後を継いだ武重に恩賞として肥後(現熊本県)一国をお与えになりました。武吉はその恩に報いたのでした。
野中少佐の湊川
以上が、『太平記』による湊川の戦いの概要です。野中少佐は幾度も読まれたはずです。基地で訓練の時も出撃の時も常に正成の「非理法権天」の幟旗をはためかせていた野中少佐が、正成同様、作戦の非を論じながらも従容として出撃したその思いは、生きては帰らじとの強い決意であり、困難は承知の上で敵艦に「桜花」を突入させるぞとの決意を込めた「湊川だよ」であったと受けとれるのです。
米軍の戦闘詳報によれば、待ち構えていた米戦闘機群と遭遇し二十分足らずで一式陸攻全滅、直掩機も壮絶な戦いを展開し、帰投できた機は僅かでした。「桜花」も力を発揮できずに海の藻屑となったのです。
野中機から鹿屋基地に向けて無線連絡はありませんでした。敵に感知されないように野中少佐は「無線封止」を命令しておりましたし、一式陸攻の各搭乗員も自分の守備位置で応戦していたのですから、無線連絡などできる時間もないまま、撃ち落されてしまったの です。
この日の夕方、鹿屋基地では「非理法権天」の幟旗が、主を待つように春風にはためいていたそうです。