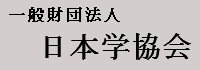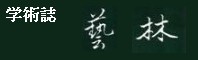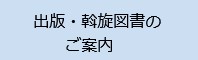『日本』令和7年4月号
「国連幻想」からの脱却を ― 女性差別撤廃委員会に参加して ―
葛城奈海 /ジャーナリスト
みなさんは、「国連」と聞くと、どのような印象をお持ちでしょうか。「国際紛争を解決する平和の殿堂」のようなイメージを抱いている日本人が多いような気がしますが、その実態はどうなのか。昨秋、スイスのジュネーブで開催された国連女性差別撤廃委員会でスピーチをした経験から、お伝えしたいと思います。
三十五秒のスピーチ
「日本の天皇は祭祀王です。カトリック教会のローマ法王、イスラムの聖職者、チベット仏教のダライ・ラマはすべて男性なのに、国連は女性差別だとは言いません。なぜ日本にだけそのように言うのですか。世界には様々な民族や信仰があり、互いに尊重されるべきです。内政干渉は許されるべきではありません」
令和六年十月十四日、「皇統(父系男系)を守る国民連合の会」(以下「皇統を守る会」)会長として女性差別撤廃委員会に非政府組織(NGO)枠で参加し、このようなスピーチを行いました。
女性差別撤廃委員会とは、女性差別撤廃条約の締約国が条約の内容を履行しているかを監督するための委員会です。締約国は定期的に、国連に報告書を提出しなければなりません。
委員会はNGOからの情報提供や、政府への対面審査を経て、「勧告」を含む最終見解を出すことになっています。「皇統を守る会」が動き始めたのは、令和二年に国連が日本政府に寄せた「質問リスト」に、「皇室典範について、皇位継承から女性を除外するという決まりがあるが、女性の皇位継承が可能となることを想定した措置についての詳細を説明せよ」という項目があったことがきっかけでした。つまり国連は、「皇位を女性が継げないのは女性差別だ」と言っているのも同然です。
背景には、日本の左派団体による「皇室典範が女性の皇位継承を排除していることは女性差別だ」という国連への陳述があります。これに沿ってひとたび勧告が出されると、こうした意見が国連の「お墨付き」を得て国内外に発信されることになります。これを阻止しようと、令和二年にも意見書を提出しましたが、今回は八年ぶりに対面で開催されることになった女性差別撤廃委員会に、新たな意見書を提出した上で、当会理事ら七名とともに乗り込み、直接意見することにしました。
ところが、私に与えられたスピーチ時間は僅か三十五秒でした。これを補うために「日本国天皇の皇位継承について」と題した英語版パンフレットを作成するとともに、視覚的にも日本の伝統文化をアピールすべく着物で当日に臨みました。満を持して臨んだスピーチ内容は、冒頭の通りです。
現場で知った「勧告」の真の意味
二日後の十六日に開催された日本関係者が集まるランチタイム報告会直前、女性陣四名でパンフレットを持って各委員に挨拶して回りました。二十三名の委員のうち言葉を交わせたのは十名弱でしたが、その際、レバノンの女性委員とのやりとりが大変印象的でした。
まず私の顔を見て、「ダライ・ラマのことを言った人ね」と言ってくださり、数多くの発言者の中で委員の記憶に残っていたことに驚きました。肝心なのは、その先です。彼女は、「私たちも伝統は尊重しています。日本に限らず他の王室のある国にも同じことを言っているので、平等の観点から日本にも言っています。推奨はしても聞く聞かないは各国の自由です」。目から鱗でした。公平性という観点で取り上げているだけで、各国の主権は尊重するという考えの委員もいたのです。彼女はこうも言いました。「私たちの国は内戦で大統領すら二年間存在していません。皇室のある日本がうらやましい」。
最終日十七日は、いよいよ内閣府、内閣官房、外務省、文部科学省、法務省、こども家庭庁、厚生労働省など三十七名から成る日本政府代表団が、委員たちの質問に答える対日審査会です。
委員からの質問は、選択的夫婦別姓や包括的性教育、慰安婦、人工妊娠中絶やアルプス処理水等々多岐にわたり計五時間にも及びました。皇統問題について言及があったのは四時間五十分くらい経ってからです。
キューバの女性委員から「天皇に関して、宗教的また文化的な側面があるのは理解しています。が、平等の原則に基づき取り上げており、法改正を検討することを求めます」と発言があったのに対し、内閣官房担当者はこう答えました。「皇位継承の在り方は歴史や伝統が背景にあり、国家の基本を為すものであるため、女性差別撤廃委員会で取り上げるのは適当ではありません」。簡潔に言い切った回答ぶりは明快で、同意する日本の保守系NGOから拍手が湧きあがりました。
ところが、これに対し、それまでほぼ議事進行に徹していた女性議長が、異例のコメントをしたのです。「皇位継承に関し、すべての差別的な法律がある国に対して同様に質問しています。自分の国スペインもそのうちのひとつなので適切だと考えます」。ここに国連の意思を見た思いがしました。
ジュネーブで得た教訓
以上を踏まえ、強く感じたことは以下の四点です。
まずは、国連から「勧告」が出されたとしても、それを聞くか否かは当事国自身の判断で、国として聞き流しても構わないということ。日本は生真面目に言われたことを聞いてしまいがちな「お国柄」ですが、主権国家として根本的な意識を「最終的には自分たちの意思で決める」と改める必要があります。主権とは即ち、自らの国のことは自ら決定し、他国からの干渉を受けない国家の権利です。
一方で、二つ目として、左派は国連の勧告を国家を超える権威として利用し、自分たちの発言力を高めようとしています。いわば「虎の威を借る狐」を増長させないために、また左派の意見が「日本国民の総意」ととらえられないために、保守側も「言うべきこと」を言わなければなりません。
三つ目に、対面での意思表示の重要性。短時間ながらスピーチしたことに加え、委員たちと直接会話して理解を求めたことが、委員に対して一定程度影響を及ぼしたことを実感しました。対日審査会で、キューバの委員から「宗教的な側面がある」という発言があったのは、その証だと言えるでしょう。なお、政府は宗教的な話はしていません。
四つ目に、着物の魅力と威力。着物効果は絶大で、まず国連入館用のQRコードを活性化する入り口から警備員はニコニコ顔。女性スタッフからも、「一緒に写真を撮ってください」と声をかけられ、着物の威力を実感しました。
皇室典範改正勧告が出されて
帰国して十一日後の十月二十九日、女性差別撤廃委員会が最終見解を発表しました。「日本の皇室典範の規定は委員会の権限の範囲外であるとする締約国の立場に留意する」としながらも、「皇位継承における男女平等を保証するため皇室典範を改正するよう勧告」しました。
前述の通り、委員会からの勧告(recommend)は「お勧め」「推奨」程度の意味合いにすぎず法的拘束力はありません。日本は、主権国家として「国家の基本」を継承する姿勢を毅然として貫いて然るべきです。
この勧告に対し林芳正官房長官は「大変遺憾であり、強く抗議し、削除の申し入れを行った」と明らかにし、「皇位継承のあり方は国家の基本に関わる事項であり、委員会が皇室典範について取り上げることは適当ではない」と指摘しましたが、その後も委員会は姿勢を変えませんでした。これを受け、令和七年一月二十九日、政府は国連への任意拠出金の使途から女性差別撤廃委員会を外すことを発表。今年度予定していた委員の訪日プログラムも中止を決定しました。その報に触れた当初、快哉を叫んだ私達でしたが、続報を知って少々拍子抜けしました。
外務省によると、日本は毎年二千万~三千万円を国連人権高等弁務官事務所に拠出しているものの、使途を指定していて、拠出金が女性差別撤廃委員会に振り向けられた例は、少なくとも平成十七年以降ないというのです。但し、拠出金が余った場合に同事務所の裁量で、同委員会に配分する可能性があるため、「転ばぬ先の杖」で先手を打ちました。つまり、同委員会に対する経済的ダメージは実質的には発生しないのです。とは言え、「抗議の意」を示したことは一歩前進と言えるでしょう。
これに対して左派系のNGOや共産党は、すぐさま拠出金制限の撤回を要求しました。
国連はGHQが看板をかけ替えた組織
総括として、日本人はまず国連への幻想を捨てなければなりません。国連は決して「平和の殿堂」ではないのです。国連、つまり国際連合とは、そもそも第二次大戦の戦勝国側の組織で、未だに敵国条項も残されています。何より忘れてならないのは、主権国家として自ら考え決断することです。
とは言え、これまで国連に届く「日本の声」は、圧倒的に左派の声が多数を占めていました。潤沢な資金のもと、日ごろから委員にロビー活動を行い、大人数で委員会に乗り込み、声を大にして「日本はこんなにひどい国だ」「助けてください」などと発信しています。そこに保守側の意見がなければ、「左派の意見」が即ち「日本国民の総意」と受け取られかねません。こうした認識が独り歩きすれば、日本の国柄が崩されてしまうことは必至です。
今回、皇室典範改正勧告とともに夫婦別姓推進の勧告も出されました。「選択的夫婦別姓」と言えば聞こえはよいですが、その実態は「強制的親子別姓」、つまり日本の共同体の最小単位である「家庭」の破壊に他なりません。導入したら最後、何世代か後には「〇〇家の墓」などというものも無くなってしまい、ご先祖様との繋がりも意識できなくなり、根無し草のような国民があふれることになるでしょう。要は、かつてGHQが行った日本弱体化工作の続きが、今、形を変えて国連主導で行われているのです。いえ、GHQとはそもそも連合国軍最高司令官総司令部なのですから、表面の看板がかけ替えられただけで同じ組織なのです。彼らの「意のまま」にさせないためには、保守側も発信を強化しなければなりません。
今回の国連での経験を通じて、日本を貶めるプロパガンダに対する「カウンター・プロパガンダの重要性」を痛感すると同時に、内政干渉に対し官民一体で立ち向かう必要性を強く感じました。「国家の基本」である皇室典範への干渉がさらに続くようであれば、日本は委員会の脱退や拠出金の実質的削減へと対応措置を強めて行くべきだと考えます。