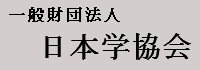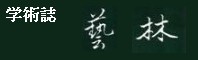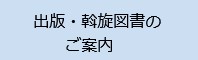『日本』令和7年4月号
大御歌に仰ぐ昭和天皇の歩み(その一)― 二十歳代前半に「摂政宮」 として―
所 功 京都産業大学名誉教授
今年は「昭和」改元(一九二五)から百年目にあたる。この機会に昭和天皇・昭和時代を振り返る企画が、すでに有力な紙誌などで行はれてゐるが、さらに色々な角度から光を当てる余地もあらう。
そこで私は、若いころ(昭和三十年代)から、毎年正月の「宮中歌会始」において披講される「大御歌」(御製)に関心を寄せてきたこともあり、公表ずみの御製を通して昭和天皇の足跡を辿つてみたいと思ふ。
それに先立つて、昭和天皇の御製を集めた主な既刊の書籍を列挙しておかう(敬称略)。
①坊 城俊民『おゝみうた/今上陛下二二一首』(昭和六十一年三月、桜楓社) ②宮 内庁侍従職編/徳川義寛氏解題『おほうなばら/昭和天皇御製集』(平成二年十月、 読売新聞社)③宮 内庁編・岡野弘彦解説『昭和天皇御製集』(平成三年七月、講談社)
※ なお、岡野抄出・写真多用『昭和天皇御製―四季の歌』(平成十八年、同朋社メディアプラン)も参照。
④副 島広之『御製に仰ぐ昭和天皇』(平成八年五月、善本社)
⑤田 所泉『昭和天皇の和歌』(平成九年十二月、創樹社)
⑥秦 澄美枝『昭和天皇/御製にたどるご生涯』(平成二十七年十二月、PHP研究所)
⑦所 功編著『昭和天皇の大御歌』(平成三十一年四月、角川書店)
昭和天皇(御名「裕仁(ひろひと)」)は、明治三十四年(一九〇一)四月二十九日、皇太子嘉仁(よしひと)親王(満二十一歳)と同妃節子(さだこ)さま(十六歳)の長男として誕生された。やがて明治四十一年(一九〇八)、祖父帝の信任篤い乃木希典(五十九歳)が院長を務める学習院の初等科に学ばれ、ついで、一般の中等科・高等科に相当する「東宮御学問所」において七年間(大正三年春から同十年春まで)特別な帝王教育を受けられた。
その御学問所を卒業されてから約半年間、皇太子(二十歳)は、第一次世界大戦後のヨーロッパ主要国(スペイン・イギリス・ベルギー・フランス・イタリア)を歴訪された。その帰国直後、生来ご病弱な大正天皇(四十二歳)が執務困難となられたため、皇太子が「摂政」に就任して父帝の代行に努められた。
父帝の代理としてご尽力
ところで、裕仁親王は幼少期から歴史と生物を好まれたが、和歌はお得意でなかつたやうである。宮内庁編『昭和天皇実録』(以下『実録』)によれば、明治四十四年(十歳)十二月、翌年正月の「歌御会始(うたごかいはじめ)」(戦後「歌会始」)に先立ち「御歌をお考えになるも……お出来にならず……側近の方針として……真の御興味から湧き出るものを詠み出されることに重点を置き」待つことにしたといふ。
それから六年後(十六歳)の正月、「御題の遠山雪にて作歌を試みられ」たが、未成年でもあつたから公表されてゐない。それを正式に出されたのは、大正十年(二十歳)の御題「社頭暁」に応じた御歌である。
1 とりがねに夜はほのぼのとあけそめて代々木の宮の森ぞみえゆく
この代々木の宮は、前年十一月に創立された明治神宮であり、その森は全国の青年たちが奉仕して植ゑた若木の林である。崇敬する明治天皇を祀る神宮を仰ぎ見ながら、若き皇太子が祈られた御心は、摂政宮となられて間もない翌十一年の歌御会始で披講された次の御歌に明示されてゐると思はれる。
2 世の中もかくあらまほしおだやかに朝日にほへるおほうみのはら
当時、数年前に内定しながら反対にあつてゐた久邇宮良子(ながこ)女王との御婚姻が確定した。ところが、翌十二年(一九二三)の九月一日、関東大震災に襲はれ、被災地を訪れて、罹災者を慰め励ますことなどに多忙を極められ、御婚儀も自粛して延期されたが、年末にはアナキストに狙撃されるなど危ふい状態でもあつた。その虎ノ門事件から一週間後の歌御会始で披講された御歌には、切実な思ひがこめられてゐる。
3 あらたまの年を迎へていやますは民をあはれむ心なりけり
さらに同十四年(二十四歳)の歌御会始で披講された左記の御歌に、立山のやうな「雄々しさに習へ」と詠んでをられるのは、「ご自身に、人の範となるやうに、おっしゃってゐる」(①の指摘)ものと解される。
4 立山の空に聳ゆるをを( 雄々)しさにならへとぞ思ふみよのすがたも
※ 以下、十二月号まで連載予定。