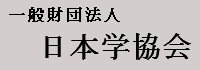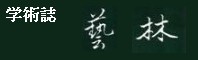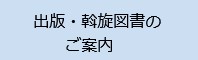『日本』令和7年4月号
【遺稿】 晩年の昭和天皇の御姿
永江太郎/(一財) 日本学協会 前常務理事
昭和天皇の晩年の御姿について、昭和六十二年の天皇誕生日の祝宴で嘔吐されてから崩御されるまでの記録を当時の侍医伊東貞三氏が刊行した「昭和天皇の晩年の想い出」(医学出版社)と、フジテレビが平成二十九年十二月二十七日に放映した「報道スクープSP激動世紀の大事件Ⅴ 昭和の時代が終わった日」の要点を抜粋した資料を、舞鶴の飯田教大氏から送って頂いた。貴重な内容と思うので、その背景を補足して紹介したい。
エピソード 一
昭和天皇と侍医の関係について、伊東侍医は厳しさの中にもウイットに富む陛下の一面を紹介している。その一例として、伊東侍医が那須の御用邸にお供した時、玄関前に沢山植えられているやぶきた茶について、専門家の説明を受けられた昭和天皇が、すかさず「私の後ろにもヤブがあるよ」と言われた。このような冗談が通じる間柄だったのである。
エピソード 二
その一方で、伊東氏が侍医に着任した時に侍医長から注意されたのは、「医者は陛下のお側に行ける職業だが、糸脈の精神を忘れてはいけないよ」の一言であったという。漢方の世界では、皇帝などの高貴な人の脈を診る時には、手首に糸を巻いて遠く下座から振れを感じて診察していた。天皇陛下のお側近くに奉仕している者は、いくら親しみを感じても、高貴な天皇への畏敬の念を忘れてはならないとの戒めであった。侍従などは歩行困難な陛下をお助けする場合でも、決してお手を引いて差し上げる事はせず、必ず腕を支えていたという。
伊東氏自身も陛下の吐血の後始末を震えながらしている時、平然とした表情で「伊東、今日は満月だよ。障子を開けてごらん、綺麗だ」と話される陛下に、首から下の体幹は物体でも、お首から上は天皇なんだ、神様なんだ、と感じたという。
看護婦もまた献身的でかつ優秀であった。昭和六十三年の大晦日、伊東侍医が当直の時に昭和天皇の呼吸が止まったことがあった。するとお側にいた日本赤十字社から派遣されていた看護婦が、すかさずお胸をタンタンと大工のようにこぶしで叩いたので、再び自発呼吸がはじまった。そして一週間延命されたのである。
平成元年の御大葬の日に公表された御製四首の中の一つは、次の歌である。
去年(こぞ)のやまひに伏したるときもこのたびも看護婦らよくわれをみとりぬ
エピソード 三
「陛下はよくひとりごとを言っておられました。聞くところによると、私が侍医を拝命する前からそうであったらしいのです」との一文には、大東亜戦争時の陛下の御姿を思い起こさせる。特に戦争が苦境に陥ってからは、一人言(ひとりごと)を言いながらお部屋の中を歩き回られる御姿が、当時の侍従や侍従武官達にしばしば目撃されていた。その原因について、私(永江)は陛下の御懸念を無視する統帥部への御不満であったと推察している。昭和天皇の的確な情勢判断と御下問で示される御指摘が統帥部には理解できなかったのである。本誌の令和三年八月号で紹介したガダルカナル作戦の第十七軍参謀長宮崎周一少将(後に中将、大本営の陸軍作戦部長)は、撤退直後の報告書の中で「(昭和天皇の戦争指導について)陛下の御心鏡には神の御心がそのまま映し給うと拝察する」と述懐している。
終戦の実現は、万策尽きた政府と大本営が国体護持に確信が持てないまま昭和天皇の御聖断を仰ぎ、自分の身はどうなっても良いとの御覚悟とともに「国体は護持できる」との確信を示されたからである。「国体を護持し得て」の詔は実現したが、占領政策からの脱却は「兆し見ゆれど」と実現していない。昭和天皇の御悩みはその後も続いて、一人言は崩御されるまで尽きることはなかった。伊東氏は「誰も相談する人がなく孤独だから」と結論したが、陛下の御憂慮はもっと深く重く、我が国の将来を見据えておられたのではあるまいか。